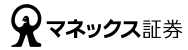
ブラウザの「X」ボタンでウィンドウを閉じてください。
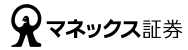
| 相対取引 |
|---|
| 取引所などを介さず、売り手と買い手が直接に取引すること。 銀行対銀行、銀行対顧客といった1対1の取引。取引価格も取引方法も当事者同士の交渉によって決まる。 |
| アゲインスト (Against) |
| 現在、保有しているポジションを市場レートで評価した場合に損失が生じている状態のことをいう。( ⇔ フェイバー) |
| アスク (ASK) |
| 外国為替取引におけるレート提示側の売値。応じる側(顧客)にとっては買いレート。ツー・ウェイ・プライスでの価格表示の際の高いほうのレート。オファー(OFFER)ともいう。( ⇔ ビッド(BID)) |
| アセット |
| 資産のこと。 |
| アセット・アプローチ (Asset Approach) |
| 為替相場決定理論のひとつで、ある時点での資産ストック量の需給関係によって相場は決まるという説。 |
| アービトラージ (Arbitrage) |
| 価格差を利用した「さや取り」を「アービトラージ(裁定取引)」と呼ぶ。異なる2つの市場の価格差を利用して利益を得ようとする取引。 例えば、「現物市場で取引されている為替レート」と、「先物取引で取引されている為替レート」の差額を利用して利益をだす手法。 |
| アマウント(Amount) |
| 「取引量」「取引単位」「取引金額」のこと。 |
| 委託介入 |
| 海外の通貨当局に介入を依頼すること。 |
| イフ・ダン・オーダー |
| 新規の指値注文または逆指値注文を出すと同時に、その新規注文が約定された場合に有効となる決済注文を、新規注文とセットで出す複合注文方式。 新規注文が約定した直後、自動的に決済注文が有効になる。この場合の決済注文は、指値注文または逆指値注文を指定する。 |
| イフ・ダン・オー・シー・オー・オーダー |
| 新規の指値注文または逆指値注文を出すと同時に、その新規注文が約定された場合に有効となるOCO(オー・シー・オー)注文を同時に出す複合注文方式。出される2つの注文は、通貨ペア、売買区分、注文金額が同じであることが条件である。 |
| 陰線 |
| チャート分析で使われるグラフの線のこと。始値、高値、安値、終値のいわゆる4本値を表したローソク足の形状で、その日の終値が始値より低い場合に黒地で表す。( ⇔ 陽線) |
| インターバンク市場 |
| 外国為替の決済機関として存在する銀行と金融機関のみが参加する外国為替市場を指し、特定の取引所は存在しない。世界中の参加者が相対取引を前提に取引が行われている。(外国為替銀行間市場ともいう) |
| インターバンクレート (Inter Bank Rate) |
| 銀行間で取引されている為替レート。 |
| ウォールストリート (Wall Street) |
| ニューヨーク市マンハッタン島南端の通りの名前。世界の金融の中心地。 ニューヨーク証券取引所、連邦準備銀行、証券会社、大手銀行などが集中している。 |
| 受渡日 |
| 取引が実現する日。 銀行間取引のルール上、取引されたポジションは約定日の翌々営業日に当該通貨が受渡しされ、取引が実現化される。 ただし、翌々営業日がニューヨーク市場または当該通貨の市場が休日と重なった場合等は、受渡日はさらにその翌営業日となる(バリュー・デイトともいう)。 |
| 売建玉 |
| 売付取引のうち決済が完了していないものをいう。 |
| 売り持ち |
| 売りポジションを保有している状態のこと。 |
| エリオット波動 |
| R.N.エリオットが確立したフィボナッチ数列を基礎とするチャート理論のこと。 相場波動の基本は、上昇5波動、下降3波動の組み合わせでできているとする。「強気相場は、悲観の中に生まれ、懐疑の中に育ち、楽観の中で成熟し、幸福感の中で消えていく。」との言葉は有名。 エリオット波動理論には、パターン・比率・時間という3つの重要な側面がある。 |
| 円転 |
| 外貨を円に転換して、円貨で運用する操作。円転換。 |
| 円投 |
| 円資金を外貨に投資して、外貨で運用する操作。円投入。 |
| オー・シー・オー |
| 2つの注文を同時に出し、一方が約定されたときには約定していない他方の注文が自動的に取り消される複合注文方式。 決済の場合は、出される2つの注文は、通貨ペア、売買区分、注文数量が同じであることが条件である。 |
| オージー |
| 外国為替取引では豪ドルを指す。 |
| オーバー・ザ・カウンター (O.T.C:Over The Counter) |
| 店頭で行う相対取引。 取引所を介さない取引全般をOTCと呼ぶ。 |
| オーバーシュート |
| 相場がチャートポイントを飛び越えるような形で、急激に行き過ぎた動きをすること。 |
| オーバーナイト・ポジション |
| 外国為替市場において、その日のうちに決済せずに翌日まで持ち越すポジションのこと。 |
| 押し目 |
| 相場が上昇しているときに、価格が一時的に下がる局面のこと。ディップ(dip)ともいう。そのタイミングで買うことを「押し目買い」という。 |
| オシレーター |
| 価格の絶対水準とは無関係に売り・買いのシグナルが発信される、上下に振幅するチャート。相場の強弱を表わす指標。 RSI、サイコロジカルライン、ストキャスティクスなど。 |
| オファー (Offer) |
| 外国為替取引におけるレート提示側の売値。応じる側(顧客)にとっては買いレート。ツー・ウェイ・プライスでの価格表示の際の高いほうのレート。アスク(Ask)ともいう。( ⇔ ビッド(Bid)) |
| オフショア市場 |
| 主に非居住者(外資)向けの金融市場。 国内市場とは切り離し、金融ルールや税制上の制約をほとんど受けないため、比較的自由な国際金融取引ができる。 |
| 外貨準備高 |
| 政府と日銀が保有している外貨の手持ち額で、輸入代金や借入金返済などの対外支払能力を示す。 主として日銀の介入によって変動する。 |
| 買建玉 |
| 買付取引のうち決済が完了していないものをいう。 |
| 買い持ち |
| 買いポジションを保有している状態をいう。 |
| 外国為替 (Foreign Exchange) |
| ある通貨を買うために別の通貨を同時に売ること。 |
| 外国為替銀行間市場 |
| 外国為替の決済機関として存在する銀行と、金融機関のみが参加する外国為替市場を指し、特定の取引所は存在しない。 世界中の参加者が相対取引を前提に取引が行われている。 インターバンク市場ともいう。 |
| 外為ブローカー |
| 外国為替市場(インターバンク市場)の仲介業者。 直物取引や外貨資金取引を仲介している外為ブローカーとしては、トウキョウフォレックス上田ハーロー株式会社が代表的。 |
| 介入 (Intervention) |
| 中央銀行が自国や他国の外国為替市場において、経済実態を反映しない相場の急変動に対して、為替相場を安定的に維持するために行う為替売買のこと。 |
| カウンター・パーティ |
| 取引相手のこと。 |
| カバー (cover) |
| 自分の持ち高を清算する方向で外国為替の売買を行うこと。買いポジションは売ること。売りポジションは買うこと。 |
| 為替差損益 |
| 為替相場の変動により発生する損益。 例えば、米ドルの買い持ちの場合、米ドルが上昇すれば利益が発生し、下落すれば損失が発生する。逆に米ドルの売り持ちの場合、米ドルが下落すれば利益が発生し、上昇すれば損失が発生する。 |
| キャリートレード |
| 低金利の通貨で資金を調達し、調達した通貨よりも金利の高い国の通貨に交換して運用し、金利差収入を得ること。 例えば、円キャリートレードとは円を調達し、日本より金利の高い通貨(米ドル、豪ドル、NZドル、英ポンドなど)で運用することである。 また、広義では、低金利である円資産を持つ国内企業、個人が金利の高い外貨で運用する場合も含まれる。 (低金利通貨売り、高金利通貨買いの資金の流れが外国為替相場へ影響する) (注) キャリートレードの巻き戻し |
| 金融政策決定会合 |
| 日銀が金融政策を決める会合。月に1~2回開く。 経済・物価の見通しや当面の金融政策の運営方針を議論する。メンバーとなる政策委員は総裁と副総裁2人、審議委員6人の合計9人。財務省と内閣府の幹部も政府代表として出席する。意見を述べ、議決の延期を求めることができる。 |
| キウィ |
| 外国為替取引ではNZドルを指す。 |
| 機関投資家 (Institutional Investor) |
| 顧客(個人・法人)から預かった資金を運用・管理する法人投資家の総称。 主たる機関投資家として、「投資顧問会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「信託銀行」、「投資信託会社」、「年金信託」等がある。機関投資家は大量の資金をまとめて運用するので、市場に与える影響が非常に大きい。 |
| 基軸通貨 (Key Currency) |
| 各国の当局が外貨準備高として保有している通貨。企業、個人が国際取引に広く使用している通貨。米ドルが世界の基軸通貨であったが、同時多発テロ以降、資金の一部がユーロにシフトされ、基軸通貨としての信頼を揺るがせた。 |
| 逆指値注文 (ストップオーダー) |
注文を出す際に、注文時点の提示価格より不利な価格を指定する注文方法。(買注文の場合には注文時点の提示価格より高く、売注文の場合には低い価格の注文。) 約定価格は指定した価格より不利な価格となることがある。 保有しているポジションを対象に、予想に反して相場が反対方向に推移した場合や損失を限定したい時に用いられることが多い。 |
| キャピタル・ゲイン (Capital gain) |
| 購入時の単価よりも売却時の単価が高いことによる利益。償還差益の場合もいう。 |
| キャピタル・ロス (Capital loss) |
| 購入時の単価よりも売却時の単価が低いことによる損失。償還差損の場合もいう。 |
| 協調介入 (Coordinated Intervention) |
| 各国の中央銀行が共同して行う介入。 |
| くりっく365 |
| 2005年7月1日に上場した東京先物取引所が運営を行っている日本唯一の公設為替取引所。 公設市場で行う取引所外国為替取引だから、透明性が高く公正な取引を目的としている。 現在、10社の外国為替証拠金取引業者が、くりっく365に参入している。 |
| クロス取引 (Cross Trade) |
| 外国為替取引では基軸通貨たる米ドルを介さない取引のこと。 ユーロ/円、 ユーロ/英ポンド、 豪ドル/NZドル など |
| クロス円 |
| クロス取引の中で、円を介する取引通貨ペアのこと。 ユーロ/円、 英ポンド/円、 豪ドル/円 など |
| ケーブル (Cable) |
| 英ポンド・ドル(GBP/USD)のスポット・レートの呼称。 |
| 気配値 (LevelまたはIndication) |
| ある時点の外国為替市場で取引されているおおよその水準、参考レート。現実に取引されているレートに極めて近いが、取引できるレートではない。 |
| 鉱工業生産指数 (米国) (Industrial Production Index) |
| 米国の製造業の鉱工業生産動向を指数化したもの。米国の製造業の生産活動の状況、設備投資の状況を反映しているため、生産動向を測る上で重要視されている。 |
| 公定歩合 (Discount Rate) |
| 中央銀行が民間金融機関に対して貸し出す際に適用する基準金利。 |
| サイクル (Cycle) |
| 株価や為替相場の変動において、上下へ波打つ循環的な動き。周期。 |
| 指値注文 |
| 売買価格を指定する注文方法。買注文の場合には注文時点の提示価格より低い価格を、売注文の場合には提示価格より高い価格を指定する。 |
| サポートライン (Support Line) |
| 支持線。レートがその線で下げ止まれば、反転し上昇に転ずるとされるレベル。( ⇔ レジスタンスライン) |
| 直物取引 (Spot) |
| 外国為替の取引が成立してから2営業日後に、外貨とその対価の受け渡しが行われる取引。スポット取引ともいう。 |
| 住宅着工件数 |
| 公共住宅を除いて、該当月に建設が開始された新築住宅件数を示す。景気動向に敏感であり、景気変動を把握する際に利用されている。個人消費動向にも影響が大きい。 |
| 証拠金 |
| 金融先物取引業者との契約に基づき、取引の売買注文に先立って、取引によって生じる一切の債務を担保するために預入れる金銭のこと。 |
| 証拠金取引 |
| 一定の資金を担保(証拠金)として預けることによって売買ができる取引のこと。 |
| 消費者信頼感指数 (米国) (Consumer Confidence Index) |
| 消費者に対してアンケート調査を行い、消費者マインドを指数化したもの。 コンファレンス・ボードは5,000人を対象とした調査で雇用重視、ミシガン大学は500人を対象とした調査で家計重視という違いがある。現在・将来に対する消費者のマインド、個人消費動向を把握する際に利用する。 |
| 消費者物価指数(CPI) (Consumer Price Index) |
| 一般消費者世帯が購入する商品とサービスの総合的な価格の動きを指数化したもの。 インフレに関する最重要指標。金融政策への影響は大きい。 |
| ショート (Short) |
| 売りポジションを保有している状態のこと。( ⇔ ロング) |
| ショートカバー |
| ショートポジションを持った(売り持ち)人が、損益を確定させたり、リスクを軽減させるために買い戻すこと。 |
| スターリング (Sterling) |
| 英ポンドのこと。 正確には、スターリング・ポンド(Sterling Pound)という。ユーロ導入前に、アイルランドの通貨であるアイリッシュ・ポンド(Irish Pound)と区別するために使われた。 |
| ストップ・オーダー (Stop Order) |
| 逆指値注文のこと。 注文を出す際に、注文時点の提示価格より不利な価格を指定する注文方法。(買注文の場合には注文時点の提示価格より高く、売注文の場合には低い価格の注文。) 約定価格は指定した価格より不利な価格となることがある。 保有しているポジションを対象に、予想に反して相場が反対方向に推移した場合や損失を限定したい時に用いられることが多い。 |
| ストップ・ロス・オーダー (Stop Loss Order) |
| 保有しているポジションを対象に、予想に反して相場が反対方向に推移した場合などに、損失を限定するため用いる注文。 |
| スプレッド |
| 外国為替レートで売値と買値の差のこと。相場の状況によっては拡大することがあります。 |
| スペキュレーション (Speculation) |
| 投機。売買差益を得ることが目的の取引をいう。 |
| スポット・レート (Spot rate) |
| 直物取引のレート。 |
| スリッページ (Slippage) |
| 逆指値注文成立時に生じる、成立レートと注文レートとの差。 |
| スワップポイント (Swap point) |
| 2通貨間の金利差に相当するもの。高金利の通貨を買い、低金利の通貨を売るとその金利差相当分を貰うことができる。その逆の場合は、金利差相当分を支払わなくてはならない。 |
| 生産者物価指数 (米国)(PPI) (Producer Price Index) |
| 米国労働省が、米国製造業者の販売価格の動向を測定・算出した物価指数。 インフレ率の判断に利用される。変動の大きい食品・エネルギーを除いたコア指数が注目されている。 |
| 製造業購買担当者景気指数 (PMI) |
| 製造業の購買担当者を対象とした景気指数。 50が景気拡大、後退の分岐点。 |
| センチメント |
| 市場心理のこと。 |
| 損切り |
| 建玉の収益が将来的に見込めないと判断した場合などに、損失を確定することを目的として決済取引を行うこと。(ロスカットともいう) |
| 対顧客市場 |
| 金融機関が個人や輸出入企業との間で外国為替取引を行う場。 |
| 建玉 |
| 買い持ち、売り持ち。 |
| ダン (Done) |
| 取引成立のこと。( ⇔ ナッシング・ダン(Nothing Done)) |
| 短資会社 |
| 短期金融市場における取引の仲介業者であり、コール資金の貸借やその仲介、または各種短期金融商品の売買等を行う会社。 東京短資株式会社等がある。日本銀行が行う殆どのオペレーションで、短資会社はその直接参加者として選定されている。 |
| 地政学リスク |
| 内戦、地域紛争や核兵器製造などで、特定地域の政治的・軍事的な緊張が高まることにより世界経済全体がうけるリスク。 主に中東情勢の緊迫を指すが、予測が極めて難しく、不確実性の増大が企業行動や消費者心理に悪影響を与え、外国為替相場が乱高下するなど、経済活動の障害になる可能性がある。 |
| ツー・ウェイ・プライス |
為替の取引レートを表示する際に、売値と買値の両方を提示すること。 売値と買値の両方を提示することで価格形成の透明性を高めている。 |
| 通貨ペア |
| 売買する2国通貨の組み合わせをいう。 為替では円と外貨以外に、ユーロ/米ドルのように外貨同士の組み合わせもある。 |
| デイ・トレード |
| 日計り取引のこと。 新規で建てたポジションを対象に当日中に決済すること。 |
| デイ・オーダー (Day Order) |
| 注文日当日のみ有効な指値注文または逆指値注文。 当日の区切りは注文日のニューヨーク午後5時までとなる。 |
| テクニカル分析 |
| 過去の価格データをチャート化して、相場の位置・方向性・相場の勢い・パターンを読み取り、将来の価格を予測する手法。 |
| デリバティブ (Derivatives) |
| 金融派生商品。先物取引、オプション、スワップなどの総称のこと。 |
| デリバリー |
| 通貨の現物受渡しのこと。保有しているポジションを対象に、反対売買の差金決済を行わず、取引総額の授受を行う取引である。当社においては、取引可能通貨は円、米ドルとユーロである。 |
| 投機筋 |
| 価格の変動によって利益を得ることを目的に売買を行う投資家のこと。 |
| 独歩高 |
| ある特定の通貨だけが上昇することを「独歩高」という。それとは反対に、ある特定の通貨だけが下落することを「独歩安」という。 |
| 仲値 |
| 各銀行が毎営業日午前10時頃のインターバンク市場の為替レートを基準にして決定する、対顧客取引レートの基準値となるレート。( = TTM) |
| 仲値不足 |
| 仲値での取引で、顧客からの米ドル買いが米ドル売りより多い状態のこと。 この場合、仲値は高めに設定される。東京市場では、日本の商取引の慣行上、5・10日(ごとうび)にあたる5日、10日、15日、20日、25日、30日の米ドル買い、決済水準が高い傾向にあるため、仲値は高めに設定される傾向がある。 |
| ナッシング・ダン (Nothing Done) |
| 取引不成立のこと。( ⇔ ダン(Done)) |
| 成行注文 |
| 売買価格を指定せず、通貨ペア、注文数量のみを指定する注文方法。 当社において、成行注文は携帯電話専用注文方法を指す。 |
| ニューヨーク 連銀製造業景況指数 (米国) |
| ニューヨーク州における製造業の活動基調や景況感を総合景況指数としたもので、業況の改善・悪化、雇用指数、インフレ指標としての仕入れ価格指数が注目されている。 |
| 値洗い |
| 未決済ポジションを日々の時価で損益計算すること。 |
| 始値 |
| 営業日開始時のレートのこと。「寄付(よりつき)」ともいう。 |
| バリュー・デイト (Value Date) |
| 取引が実現する日。 銀行間取引のルール上、取引されたポジションは約定日の翌々営業日に当該通貨が受渡しされ、取引が実現化される。ただし、翌々営業日がニューヨーク市場または当該通貨の市場が休日と重なった場合等は、バリュー・デイトはさらにその翌営業日となる。(受渡日のこと) |
| ビッド(BID) |
| 外国為替取引におけるレート提示側の買い値。 応じる側(顧客)にとっては売りレート。ツー・ウェイ・プライスにおける価格表示の低いほうのレート。( ⇔ アスク(ASK)) |
| 必要証拠金 |
| 新規建玉に必要な担保金。 |
| 非農業部門就業者数 (Non Farm Payrolls) |
| 毎月第1金曜日に米雇用統計として発表される非農業部門に属する前月の就業者数をいう。 現在、外国為替の変動に最も影響を与える重要な米経済指標である。 同時に失業率、週平均労働時間や平均賃金なども発表され、時間当たりの平均賃金の伸び率は賃金インフレの指標でもあり重要とされている。 |
| ファーム・プライス (Firm Price) |
| 実際に取引することが可能なレート。 |
| ファスト(注文) |
| 取引画面において、当社が連続的に提示する最新価格をクリックすることで発注する注文方法。 注文時の提示価格を基準として、お客様ご自身でスリッページ(※)の幅を設定できます。 ※注文価格と約定価格の差のこと |
| ファンダメンタルズ (Fundamentals) |
| 経済の基礎的条件のことで、経済成長率、国際収支、為替レートなどをいう。 |
| ファンダメンタルズ分析 (Fundamentals Analysis) |
| 価格を予想するために経済データを使う手法。 |
| フィラデルフィア 連銀製造業業況指数 (米国) |
| フィラデルフィア地区連銀がペンシルバニア、ニュージャージー、デラウエア州の製造業における景況感や経済活動の現状を示したもの。 非農業部門の就業者数、失業率、製造業の新規受注・在庫、平均賃金、個人所得など11項目から構成され、各項目について1ヶ月前と比較した現状と6ヶ月後の期待を、「良い」「同じ」「悪い」の中から選択させ指数化したもの。 |
| フィボナッチ級数 |
| 13世紀のイタリアの数学者であるレオナルド・フィボナッチが発見したもので、このフィボナッチ級数がエリオット波動理論の数学的基礎となっている。 1.618や0.618、0.382という数値は、「フィボナッチ級数」または「黄金分割比」といわれ、相場にもさまざまな形で応用されてきた。 |
| フェイバー (Favor) |
| 現在、保有しているポジションを市場レートで評価した場合に利益が生じている状態のことをいう。( ⇔ アゲインスト) |
| フェデラル・ファンド (FF) (Federal Funds) |
| 米国の市中銀行が連邦準備銀行(米国の中央銀行)に預けている無利息の準備預金のこと。 |
| フォレックス (Forex) |
| 外国為替(Foreign Exchange)の省略形。FXともいう。 |
| フォワード (Forward) =先渡し取引 |
| 将来の一定時点での価格を現段階で約定する取引。 |
| プライス (Price) |
| 外国為替市場で取引される外国為替レートのこと。実際にそのレートで売り買いができる。 |
| ベージュブック (Beige Book) |
| 米国の地区連銀景況報告のこと。 表紙の色がベージュ色をしているため、このように呼ばれる。米国の12地区連銀が管轄地域の経済状況や景気動向を収集し、FOMCに提出する。 FOMCが開催される2週間前の水曜日にFRBより公表される。 |
| ベア (Bear) |
| 相場が下落すると予想すること。「ベア(Bear)」とは熊のことで、熊は立ち上がって、腕を(前足)を上から下へ振り下ろして攻撃することから、弱気派を「ベア(Bear)」と呼ぶ。 |
| ヘッジ (Hedge) |
| 将来の価格変動リスクを回避、軽減すること。 ある取引から生じるリスクに対して、反対方向のリスクを持つ取引を行うことによってリスクの回避、軽減をしようとする方法。 |
| ヘッジ・ファンド |
| 外国為替や株式、債券などへの投資にあたって、先物やオプションなどの金融派生商品(デリバティブ)での多額の運用も行い、収益を追求するファンド。 一般の公募の投資信託とは異なり、主にオフショアのケイマンなどのタックスヘイブン(非課税国地域)に拠点を置き、私募のパートナーシップとして設立され、ハイリターンを追及し、運用成果の一部を運用担当者が成功報酬として獲得するという形が多い。 |
| ヘッド・アンド・ショルダーズ (Head & Shoulders) |
| チャート・パターンのひとつであり、典型的な天井(高値をつけて下落に転じるポイント)の形を示す。 「肩→頭←肩」の形となっていることからこう呼ぶ。仏像が3体並んでいるようにも見えるので、日本では「三尊型」ともいう。下げ相場の安値圏でできる逆の形を「ヘッド・アンド・ショルダーズ・ボトム=逆三尊型」という。 |
| ポジション (Position) |
| 買い持ち、売り持ち、未決済の建玉。 |
| ポジション調整 |
| 現在保有している持ち高を減らすため、一部を反対売買し決済すること。 |
| 保証金 |
| 取引の担保となるお金。 |
| ボラティリティ (Volatility) |
| 外国為替取引では為替レートの予想価格変動率。 |
| マイナー・カレンシー (Minor Currency) |
| 非主要通貨。メジャー・カレンシー以外のすべての通貨の総称。 |
| マイン (Mine) |
| 主にインターバンク市場の取引において取引通貨を「買った」という意味。( ⇔ ユアーズ) |
| マーク・トゥー・マーケット (Mark To Market) |
| 保有するポジションを実際の市場レート(マーケット・レート)で時価評価すること。 |
| ミシガン大学消費者信頼感指数 (米国) |
| ミシガン大学が消費者のセンチメントを指数化したもの。 コンファレンス・ボードが作成している消費者物価指数・小売売上高などと並び、消費者の動向を知るうえで欠かせない指標。ただ、コンファレンス・ボードが作成しているものに比べてサンプル数が少ないこと(約5,000件対、約500件)が弱点である。 同指標で強めの数字が出ると、かなりの確率で「個人消費の増加」「貯蓄率の低下」が生じる。 |
| メジャー・カレンシー (Major Currency) |
| 主要通貨。 世界中の外国為替市場で、多くの市場参加者が頻繁に売買している通貨のこと。現在ではUSD(米ドル)、JPY(日本円)、EUR(ユーロ)、GBP(英国ポンド)、CHF(スイス・フラン)。 |
| 約定 |
| 取引が成立すること。 |
| ユアーズ (Yours) |
| 主にインターバンク市場の取引において取引通貨を「売った」という意味。( ⇔ マイン) |
| 陽線 |
| チャート分析で使われるグラフの線のこと。 始値、高値、安値、終値のいわゆる4本値を表したローソク足の形状で、その日の終値が始値より高い場合に白地で表す。( ⇔ 陰線) |
| 呼値 |
| 値動きの最小単位のこと。ドル円の場合は0.01円(1銭)。 |
| 寄付き |
| マーケットが始まったときに、最初についた値段。 |
| リーブ・オーダー (Leave Order) |
| 指値・逆指値注文などを値段や有効期限を指定して銀行等取引の相手方に預けること。あるいはその注文のこと。 |
| 利食い |
| 収益が確定することを目的として決済取引を行うこと。 |
| 両建て |
| 同じ銘柄で買いと売りのポジションを同時に持つこと。 |
| レジスタンスライン (Resistance Line) |
| 抵抗線。レートがその線で上げ止まれば、反転し下落に転ずるとされるレベル。( ⇔ サポートライン) |
| レパトリ(エーション) (Repatriation) |
| 資金の国内への還流。外貨建て資産を売り、自国通貨に交換して国内に送金すること。 |
| レバレッジ (Leverage) |
| 「てこの原理」。レバレッジを効かせることにより、小額の資金で大きな金額の取引を行うことができる。 |
| レンジ相場 |
| ある一定内の範囲で値段が推移する相場のこと。ボックス相場ともいう。 |
| ロスカット |
| 建玉の収益が将来的に見込めないと判断した場合などに、損失を確定することを目的として決済取引を行うこと(損切りともいう)。 |
| ロスカット・ルール |
保有ポジションの損失が一定損失限度(当社FX PLUSでは30%以下)を超えた場合に、自動的に保有ポジションの損切りを行うルール。 ※ 以前のFX口座(FXproを除く)を開設されていたお客さまは、ロスカット基準率が20%となっています。 |
| ロールオーバー |
| 建玉を取引営業日当日中に決済しない場合、当未決済建玉はニューヨーク時間の17:00で、毎営業日、自動的に先送りするための手法。 |
| ロング (Long) |
| 買いポジションを保有している状態のこと。( ⇔ ショート) |
| ロンドンフィキシング |
| ロンドン市場の16時ごろ。東京市場の仲値公示時のように相場の動意が見られやすいことをいう。 |
| ADP雇用指数 |
| 全米約50万社の顧客を持つ民間の給与計算代行会社であるADP(オートマティック・データ・プロセッシング社のデータを用いて、経済予測会社マクロエコノミック・アドバイザーズが予測する民間雇用指数。 非農業雇用者数の基礎統計となる事業所調査は約4000万人の給与データを基に算出されていることから、非農業部門雇用者数の有力な先行指数とされている。2006年5月から発表された新興の米経済指標である。 |
| ASK |
| 外国為替取引におけるレート提示側の売値。応じる側(顧客)にとっては買いレート。 ツー・ウェイ・プライスにおける価格表示の高いほうのレート。OFFER(オファー)ともいう。( ⇔ BID) |
| AUD |
| 豪ドルのこと。 |
| BID |
| 外国為替取引におけるレート提示側の買い値。応じる側(顧客)にとっては売りレート。 ツー・ウェイ・プライスにおける価格表示の低いほうのレート。( ⇔ ASK) |
| BOE (Bank of England) |
| 1694年に設立されたイギリスの中央銀行。 |
| BOJ (Bank of Japan) |
| 日本銀行のこと。 |
| BRICs |
| ブラジル(Brazil)、ロシア(Russia)、インド(India)、中国(China)の4カ国の英語の頭文字をとった造語である。人口も多く、今後、著しい経済成長が期待される新興大国である。商品を売り込む市場としても、資源を大量に消費する国としても、生産基地としても、世界経済に大きな影響を与える可能性を秘めていることから大いに注目されている。 |
| CAD |
| カナダドルのこと。 |
| CHF |
| スイスフランのこと。ラテン語表示で「Confoedratio Helvetia Frac」の略語である。ユーロ導入前に、フランスフラン(FFR)と間違いを防ぐためにCHFにして区別した。したがって、スイスフラン・円はCHF/JPYと表示される。 |
| CNY |
| 人民元のこと。 |
| EBS |
| スイスEBS社が行っている外国為替取引における電子ブローキング・システム。 外為ブローカーに頼らずに、世界の各銀行のディーリングルームに設置された端末から直接為替取引を行うことができる。 現在、東京市場において、米ドル/円、EUR/米ドルなどの主要通貨の取引の80%以上はEBSを通じて行われている。 |
| ECB (European Central Bank) |
| 欧州中央銀行のこと。 1998年6月に設立。本部はドイツのフランクフルト。 |
| EUR |
| ユーロのこと。 |
| FIFO (ファイフォ) |
| FIFO(ファーストイン、ファーストアウト)とは、「先入れ・先出し」という意味で、FXの決済をする建玉の順番を表わす。 通常の決済方式では、お客様ご自身が建玉を選択して決済を行うが、FIFO方式では、最も古い建玉から順番にシステムが自動で決済を行う。 |
| FF(Federal Funds) |
| 米国の市中銀行が連邦準備銀行(米国の中央銀行)に預けている無利息の準備預金のこと。 |
| FFレート (Federal Funds Rate) |
| 米国の市中銀行が連邦準備銀行(米国の中央銀行)に預け入れるフェデラル・ファンドを調達するために銀行間市場において無担保で資金を貸借する場合の金利。 FFレートは米国の政策金利として位置付けられている。ちなみに、日本の金利では、無担保コール翌日物金利に相当する。 |
| FOMC (Federal Open Market Committee) |
| 連邦公開市場委員会。 米国の連邦準備制度の金融政策に基づく公開市場操作(マネーサプライの調節、金利・為替水準の誘導等)の方針を決定する。 FRBの理事7名、ニューヨーク連銀総裁1名、地区連銀総裁4名の合計12名で構成されており、約6週間ごとに年に8回、火曜日(2日間の場合は水曜日にまたがる)に定例会合を開催し、3週間後に議事録を公表している。 |
| GBP (Great Britain Pound) |
| 英ポンドのこと。 |
| GDP (Gross Domestic Product) |
| 国内総生産のこと。 |
| GTC (Good Till Cancel) |
| 期限に定めがなく、取消しをしない限り無期限に有効である注文。 |
| HKD |
| 香港ドルのこと。 |
| IFD (イフダン) |
| 新規の指値注文または逆指値注文を出すと同時に、その新規注文が約定された場合に有効となる決済注文を、新規注文とセットで出す複合注文方式。 この場合の決済注文は、指値注文または逆指値注文を指定する。 |
| IFD・OCO (イフダン・オー・シー・オー) |
| 新規の指値注文または逆指値注文を出すと同時に、その新規注文が約定された場合に有効となるOCO(オー・シー・オー)注文を同時に出す複合注文方式。 出される2つの注文は、通貨ペア、売買区分が同じであることが条件である。 |
| IFO指数 |
| ドイツの経済・社会・政策研究を行う非営利の公的研究機関IFO経済研究所が発表するドイツの約7,000社を対象とした景気先行指数。 IFO経済研究所はドイツ6大経済研究所のひとつ。 |
| IMM通貨先物 |
| シカゴ・マーカンタイル取引所に開設された国際通貨先物市場。 毎週発表されるIMM投機筋のポジションは、為替市場の縮図を表しているとの見方もあり、市場関係者の関心も高い。 |
| ISM製造業景気指数 |
| 米供給管理協会が発表する「製造業」における景気転換の先行指標。同協会が400社以上の企業の購買部に対してアンケート調査を実施して作成。 企業の景況感を反映し景気転換の先行指標とされることから、注目度は極めて高い経済指標である。50%が景気動向の良し悪しを測る分岐点となり、50%を上回ると景気拡大、下回ると景気後退を示唆する。なお、「非製造業」に関しては、ISM非製造業景気指数がある。 |
| JPY |
| 日本円のこと。 |
| NDF (Non-Deliverable Forward) |
| 元本の受渡しをしないで、期日の差金だけを決済する為替先物取引のこと。 差金決済は、決済期日のあらかじめ決められた公表レートとの差を元本に乗じた金額で行い、該当通貨を用いず、通常米ドルで行われる。先物市場が未成熟だったり、資本の流出規制のある国の通貨(韓国ウォン、人民元、インドルピー、フィリピンペソ、台湾ドルなど)に適用され、元本国の通貨のリスクヘッジに用いられる。 |
| OCO (オー・シー・オー) |
| 指値注文と逆指値注文の2つを同時に出し、一方が約定された時には約定していない他方の注文が自動的に取消される複合注文方式。 出される2つの注文は、通貨ペア、売買区分、注文金額が同じであることが条件である。 |
| OFFER |
| 外国為替取引におけるレート提示側の売値。
応じる側(顧客)にとっては買いレート。ツー・ウェイ・プライスにおける価格表示の高いほうのレート。 ASK(アスク)ともいう。( ⇔ BID) |
| OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) |
| 石油輸出国機構のこと。 産油国間の石油政策調整や原油価格の安定化を図るために1960年9月に設立された。現在、イラン、イラク、サウジアラビア、クウェート、カタール、アラブ首長国連邦(UAE)、リビア、アルジェリア、ナイジェリア、インドネシア、ベネズエラの11カ国が加盟している。本部はオーストリアのウィーンにある。 |
| RBA (Reserve Bank of Australia) |
| オーストラリア準備銀行のこと。 |
| RBNZ (Reserve Bank of New Zealand) |
| ニュージーランド準備銀行のこと。 |
| SGD |
| シンガポールドルのこと。 |
| TTB (Telegraphic Transfer Buying Rate) |
| 対顧客電信買相場。仲値(TTM)に銀行の手数料分として1円を差し引いたレートのこと。 |
| TTM(Telegraphic Transfer Middle Rate) |
| 各銀行が毎営業日午前10時頃のインターバンク市場の為替レートを基準にして決定する対顧客取引レートの基準値となるレート(仲値ともいう)。 |
| TTS (Telegraphic Transfer Selling Rate) |
| 対顧客電信売相場。仲値(TTM)に銀行の手数料分として1円を上乗せしたレートのこと。 |
| USD |
| 米ドルのこと。 |
| ZAR |
| 南アフリカランドのこと。 |
| ZEW 景気期待指数 (独ZEW) |
| ドイツの欧州経済研究センターが発表する経済指標のこと。 アナリスト、市場関係者約350名に質問状を送付、DI方式で指数を作成。 6ヶ月先の景気が良くなるか、悪くなるかを質問。IFO指数には1ヶ月、鉱工業生産指数には6ヶ月の先行性を持つ。 |