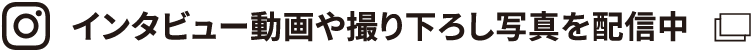お金は信頼できる
コミュニケーションツールである東野唯史×平田はる香×徳谷柿次郎
全国47都道府県を飛び回るエディトリアルカンパニーHuuuuが主催する、お金について考える長野県発のトークイベント「かっこいい借金ってなんだ?」。その特別版として「かっこいいお金の使い方ってなんだ? sponsored by MONEX」を長野県諏訪市で開催しました。今回はその様子をレポートします。
司会の徳谷柿次郎さんは、Huuuuの代表であり、編集者。地元と仕事をテーマにしたWEBメディア「ジモコロ」などのコンテンツ作りを手掛けています。出身は大阪府で35歳で長野に移住。県内でオフィスコミュニティ<MADO/窓>とスナック<夜風>を営んでいます。
一人目の登壇者は、長野県諏訪市でリユースショップを営む<ReBuilding Center JAPAN(通称・リビセン)>代表取締役の東野唯史さん。家屋や工場の解体現場に出向き、レスキュー(買取)した古材や古道具を販売しています。イベントの会場も、リビセンをお借りしました。また、諏訪市でまちづくりに取り組む<すわエリアリノベーション社>の代表取締役でもあります。
もう一人の登壇者、株式会社わざわざ代表取締役の平田はる香さんは、2009年に長野県東御市でパンと日用品のお店<わざわざ>をスタート。山の上というロケーションにも関わらず、人気を呼びます。現在は6店舗を経営し、ECサイトも2つ展開中。昨年、ローカライズされたコンビニ型の店舗<わざマート>も立ち上げました。
実はお金こそが一番ラクで、
信頼できるコミュニケーションツール
徳谷 お金に対するイメージから聞かせてもらいたいのですが、怖いとか感じますか?
東野 今のところ怖いとは感じたことはないですね。共同代表の妻には「お金はないけど心は錦だよね」ってよく言われます(笑)。そう言われるということは、執着がないんだなと。個人の通帳の残高もマジでわかってない(笑)。基本的な生活費は僕の個人口座から出る流れになっているんですけど、妻は妻の個人口座がありますし、彼女が何にいくら使っているのかもわからないです。
平田 自分のお金に関して執着がないというのは、東野さんとまったく同じです。今、日本円を現金ではほとんど持っていません。というのも、NISAとか外貨預金とか最初に設定するのは大好きで、限度額いっぱいに積み立て設定したものの、管理するのが苦手で、アクセスできないから設定を変えられないんですよ。本当は設定額を変えたいんですけど、勝手に運用され続けています(笑)

お金に対するイメージの話に戻すと、私は、お金は素晴らしいコミュニケーションツールだと思っていて。たとえば、好きなお店で店員さんに声を掛けるのは気が引けても、そこでいっぱいお買い物をしたり、毎月食べに行ったりすることで〝好きだー!″と表現できるじゃないですか。事業を始めてからは、その〝好きだー!″を、お金を介してもらえるようになりました。
徳谷 僕は、闇金に手を出してしまった親父の息子なので(笑)、お金への執着があるほうなのですが、やはりお金を得ようとする行為は、選択を広げてくれますし、頑張ろうとするモチベーションにもなって、いいことだと思います。で、お二人は長野に移り住み、こうして根を張り、事業をなさっていますよね。ローカルにおけるお金の使い方は、都市の消費的な生活とは違いますか。
東野 さっき平田さんが話していたことに近いと思うんですが、お金って、受け取り手の顔が見えるとより使いたくなりますね。応援したい駆け出しの作家さんの作品を応援のために買ったり、尊敬する人の作品をお守りのように手元に置いておくために買ったり。お金は回ってなんぼみたいなところがあるじゃないですか。その回ったお金がどこに行くのかということは、こっちにきてから気にするようになりました。
平田 私は創業当初、〝お金というものは不要なのではないか″と錯覚していて、私が欲しいものであればお金以外でも、パンと交換していたんです。一番大きかったのが、「大工さんが家屋を修繕してくれる費用として、1年間50万円うちで好きなだけ買い物する権利」。ただ、このシステムをやっていくと、私が欲しくないものを持ってくる方も出現するんですね。昨日の残り物をタッパに詰めて持ってくるとか。スタッフも困るわけです、持ち込まれたものが私の欲しいものか判断できないし。税理士さんにも指摘を受けまして。それで学んだのが、交換というシステムにおいてお金が一番ラクで、みんなが幸せだということでした。だから、古くからお金が使われてきたのだなあと。
徳谷 面白いですね。Huuuuが運営している長野市のコミュニティオフィス「MADO」でも、コミュニティ代として月6000円払ってもらっているんです。なんでもかんでも無料にすればいいわけではなくて、お金を払うことで行きやすくなるんですね。継続的な関係性を作るには、お金を払うことに意味があると実感しています。東野さん、リビセンのレスキューの仕組みはいかがでしょう?
東野 レスキューという、家屋や工場を解体して古材や古道具を引き取る作業には、サポーターズの方々にお手伝いをしてもらっていて、報酬は払っていませんが、社宅の一角に無料で泊まれる部屋を用意して、昼と夜は無料でまかないも食べられます。うちのスタッフがサポーターの地元に遊びに行ったり、サポーター同士が仲良くなったり、いろんな交流も生まれています。お金は介在しないけれども、サポーターズが時間を使ってくれることに対して、僕らは真摯に向き合っています。タダで労働力を手に入れられていいねというような見られ方もするのですが、お金を払って「その分働いてね」と言った方が、ある意味で気はラクかもしれません。こちらが労働力を搾取するマインドだったら、絶対に破綻するシステムでも続いているということは、お互いが満足できる落としどころになっているのかなと思います。お金を払わないからこそ、受け身でいることが大事だと思っていて、こちらからは「来て」とか声を掛けないようにしています。

事業計画なくして夢を語るなかれ⁉
ローカルビジネスの最前線
徳谷 リビセンは、リユースショップですが、従来のなんでもあるタイプのお店ではなく、しっかりとしたコンセプトに基づいた世界観があります。ただ、古材は活用する人がそこまで多くなく、循環させるのが大変という話も聞いたことがあるのですが。
東野 古材は古道具の1/5も売れません。やっぱり生活に取り入れづらい。どうしたら広がるか、リサイクル事業をやっている人に相談したことがあるんですが、「リサイクルは技術で、リユースは文化だ」と言われたんですね。リサイクルに多い木材をチップにするとかアップサイクルは技術革新が進んで、効率よく安くできるんだけど、リユースはそのものの価値をきちんと認識してもらう文化を作っていかない限りは循環していかない。今は、どうやったら古材の扱い方そのものを〝文化″に変えていけるか、すごく考えています。
徳谷 平田さんは、諏訪にコンビニ型<わざマート>の2号店ができたばかりですね。ラインナップが面白くて、行くたびにいろいろ買っちゃうんですが、在庫管理など、なかなか大手ができない特殊なことをやっていますよね。
平田 わざマートは同業の小売業の人がくると、物量と種類の多さにすごく驚かれます。商品選択、物流網の組み方、在庫管理とバックエンドが大変なのが一発でわかる。そこをうちは面倒がらない。むしろ、仕組みを作ることに面白さを感じています。もともと、山の上にわざわざ来てくださってありがとうございますという意味で<わざわざ>という名前をつけたくらいで、手のかかることがすごく好きで得意なんですよ。他が絶対できないだろう思うことを、合理性を持った仕組みにしたのが<わざマート>です。
あと大事なのは教育ですよね。筋のいい仕入れができる人を増やす。一例として、冬だからアイスが売れないとバイアスがかかっていて、店長は積まなかったんです。トライしたことがないのに売れないという判断をするのは違うので、失敗してもいいから夏と同じ量を積むように指示したら、バカ売れしたんですよ。データを見ることを徹底的に教えると、ロスがなくなって、売上も伸びて、ものすごくモチベーションも上がるんです。

徳谷 お二人は、これからお店をやりたい人の相談にのることもあると思うんですが、どんな点を重視してアドバイスしていますか。
平田 私は〝数字″の一点です。原価率がどのくらいで、家賃がいくらだから、売上がこのくらいないとやっていけない、という構造を理解できていなければ破綻するのが目に見えているじゃないですか。とにかく事業計画をちゃんと立てる! …と事業を始める前の私自身に言いたい(笑)。厳しいことを言うようですが、数字を管理できないと夢を語る資格もないよって思いますね。
徳谷 ちょっと会場の空気がざわつきましたが(笑)
平田 まったく事業計画を立てていなかった自分への反省も含めての話です(笑)
東野 (笑)。平田さんの話に加えたいのが、将来お店をやりたい人のよくある言い訳が〝お金がないから貯めている″。お金は借りられるので、貯める時間は正直なところ無駄です。
平田 そうなんですよ。事業計画をきちんと書いて、銀行に持って行って、ロジカルに説明できれば、お金は借りられます。
東野 逆を言えば、数字を立てて計画を作ったのに借りられない事業なら、やらないほうがいい。僕ら数字、数字と言ってますけど、その根拠は情熱だったりスキル。それあっての数字であり事業計画です。
これまで投資してよかったもの、
これから投資したいこと
東野 経営していると、お金で解決できることってすごくラクに感じませんか。僕は、貸してもらえるうちが花なので、借りればいいというスタンスです。
平田 わかります。できればすべてをそうしたいくらい(笑)
東野 一方で、採用が上手くいかない、スタッフが育たないという、お金で解決できない問題は人が頑張るしかない。
平田 私は、採用が苦手で…。本来、面接に来た人の悪いところもちゃんと見抜いて、それがチームにどう作用するか考えないといけないのに、いいところばかりを見てしまう。なので、2、3年前に採用チームを作って私は離れたんです。そのチームでは、実店舗とWEBで採用説明会を行い、そこに参加した人にだけ採用窓口を開くようにして、去年は70人の応募があり、2人採用しました。本人からどういう働き方がしたいのか聞き、それにはこうしたスキルアップが必要だけどできるか尋ねます。同意を得られたら、そのためのプログラムや目標を一緒に作ります。みんなの合意形成がなされてない中で一律の教育をしていた頃に比べると、人が育つようになって、うちにとっては今のところベストな形ですね。
東野 うちでは採用やチームビルディングはほぼ妻がやっているんですが、応募者の約半分は、先ほどお話したサポーターズの経験者です。サポーターズの仕事は、ひたすら3階まで荷揚げするとか、ホコリまみれで掃除をするとか結構大変なんですよ。それでも働きたいと思ってくれて応募してくれても、カルチャーフィットせず辞めていく人もやはりいます。これはスタッフにも周知していることなのですが、人が去っていくことにネガティブな感情を抱かないようにしています。というのも、人が辞めると僕や妻以上に、スタッフがショックを受けるんですね。人材確保が大変な今、何とかとどまってもらうために働きやすい環境を作る方向に目が向きがちなんですけど、もっと大事なのは、リビセンで働くことが、その人の人生にとって本当にいいのかどうかを考えることなのではないかと。離れるほうが幸せなのかもしれない。こちらも、離れる方も、そういう気づきが得られるようなコミュニケーションを取るようになってから、すごくチームの状態がよくなりました。

徳谷 最後に、お二人にとって投資している、もしくはしていきたいものを教えてください。
平田 〝筋肉″です。実は、ECサイトのリニューアルに失敗して、年間売上が半分になってしまったんです。あの時はもう、いよいよ個人資金を投入する日がくるぞと。その日に備えて投資していた資産を現金化できるようにしようと、口座に必死にアクセスしていました。結局わからなかったし、ECの売り上げも復活して事なきを得たのでそのままですが(笑)
徳谷 最初の話がここで繋がるんですね(笑)
平田 全財産投入して何年持たせられるか、頭の中でざっと計算したら本当に怖くなってしまって…。あの時、メンタルは体力に比例するんだとつくづく感じました。もともと私は虚弱で自然派になったという文脈があるんですけど、改めて健康について捉え直して、筋肉に辿り着いたんです。それで、筋トレを始めました。肉体的な状態が精神状態に影響を及ぼすことを痛感したので、先に体を鍛えればメンタルが元気になると発想を転換したんです。健康=筋肉。筋肉はすべてを跳ね返します!(笑)
東野 過去の話になってしまうんですが、僕が投資してよかったのは〝時間″です。新卒で入った会社では、なるべく早く一人前のデザイナーになりたくて、自ら願い出て月150時間くらい残業していたんです。スキルが伸びたのでそこは辞めて世界一周の旅に出て、帰国後、フリーランスに。その時代が4年くらい続くんですけど、その頃は月々の定額で何でも請け負っていたんですよ。デザインはもちろん、現場で左官や大工をしたり、解体作業も材料を探すこともすべて月額内でやっていました。そうすると、いろんな面白い仕事がくるんです。そういう案件はいろいろ試せるのでデザインのスキルは上がるし、古材の知識は増えるし、人との繋がりも広がりました。そうした時間の投資をしたからこそ、こうしてリビセンというやりたいことを実現できたんです。もちろん、ライフステージの中で、時間の投資はできるタイミングは限られているとは思うので、時間を投資するか、お金を投資するか、その時々で何に投資するかを選んでいけるといいですよね。


東野 唯史
ReBuilding Center JAPAN共同代表、株式会社すわエリアリノベーション社 代表取締役。名古屋市立大学芸術工学部卒。2012年に東京・蔵前にある「Nui. Hostel&Bar Lounge」をきっかけに店舗設計を主軸に活動を開始し2014年に妻の華南子と合流、2016年に長野県諏訪市にてReBuilding Center JAPANを創業。2022年にすわエリアリノベーション社を設立し、エリアリノベーションに取り組む。

平田はる香
株式会社わざわざ代表取締役。2009年長野県東御市の山の上に趣味であった日用品の収集とパンの製造を掛け合わせた店「わざわざ」を一人で開業。2017年に株式会社わざわざを設立した。2019年東御市内に2店舗目となる喫茶/ギャラリー/本屋「問tou」を出店。2020年度で従業員20数名で年商3億3千万円を達成。2023年度に3,4店舗目となるコンビニ型店舗「わざマート」、体験型施設「よき生活研究所」を同市内に出店。また初の著作「山のパン屋に人が集まるわけ」がサイボウズ式ブックスより出版された。

徳谷柿次郎
株式会社Huuuu代表取締役。全国47都道府県を取材するローカルメディア『ジモコロ』編集長を8年間やりきって、現在は標高700mの山奥に暮らす。生活圏内に『スナック夜風』『パカーンコーヒースタンド』といったリアルな場の編集、独立系出版、Podcast制作など、思いついたことをとにかく形にする衝動に駆られている。自著に『おまえの俺をおしえてくれ』(風旅出版)がある。