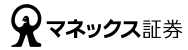
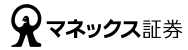
情報提供:(株)東洋経済新報社
掲載は、全国4取引所(東京、名古屋、札幌、福岡)。なお、掲載されているデータのうち、コメント記事と特色、業績予想・ファイナンス予想は、四季報編集部の独自の取材による判断が含まれます。また、業績・財務関係の実績データは決算短信より収載、株主・役員・住所等は会社への調査に基づいてます。
コードは、証券コード協議会の定める4桁証券コード(銘柄番号)です。社名は、原則として登記社名を掲載、社名の前に「株式会社」がつく場合には(株)を付記していますが、社名の後ろにつく場合には一律省略しています。 当該会社が通称を採用している場合には、その通称社名を掲載しています。
本決算期(事業年度の末日)を示します。月末決算の会社は「日」を省略しています。会社法の施行により、臨時株主総会での決議または定款に定めのある会社は取締役会の決議のみで随時配当することが可能となり、中間配当制度の有無の意味合いが低下したために、06年4集より制度ありを示す「中配」の掲載を中止しています。
設立は、登記上の設立年月を表示します。登記上の設立年月が名目的な場合は実質的な設立年月(例えば実質存続会社の設立年月)を記載しています。原則として株式会社の設立年月を掲載しています。
戦後、証券取引所が再開した後に最初に上場した市場の上場年月を表示しています。市場を変更した場合は最初に上場した年月を表示します。
会社の事業内容、業界での地位、資本系列、沿革などを要約してあります。なお、銀行の順位は直近の本・中間決算期末の資金量(譲渡性預金、積金、金融債発行銀行の債券、信託勘定を含む)によるものです。
直近本決算期(末尾の< >に時点を表示)の部門別売上構成比率で、単位は%(※)。
※ 分母となる売上高は原則として内部売上高控除後の数値ですが、内部売上高を含めた値を使用している場合もあります。
カッコ内は各部門の売上高利益率で、「-」(マイナス)は赤字を意味します(算出の際、セグメント間の内部売上高を含めて計算しており、分子となる利益は原則営業利益ですが、報告セグメントのセグメント損益の場合もあります)。 単位はいずれも%。
【連結事業】は連結ベース、【単独事業】は単独ベースの部門別売上高構成比です。
【海外・輸出・貿易】
それぞれ売上比率で、基準は売上構成比率に準じています。【海外】は連結海外売上比率、または建設業の海外工事比率、【輸出】は単独事業の場合の総販売実績に占める輸出比率、【貿易】は商社などの売上げ(一部仕入れも含む)に占める輸出入・三国間取引の比率です。
直近本決算期(末尾の< >に時点を表示)の部門別売上構成比率で、単位は%(※)。
業種コード、業種名は、証券コード協議会による33業種分類に準拠しています。
2つの段落で構成され、前半は主に今期または来期の業績見通しを述べた業績記事欄です。原則として業績予想数字は1期目(今期)について、前期比または前号比で解説しています。業績予想数字2期目(来期)について記述する場合は、文頭に「○年○月期は」と決算期を明記しています。後半が各社の最近のトピックス、中期展望、会社の課題などを書いた材料記事欄となっています。
記事の内容はあくまで四季報編集部の取材に基づく、独自の見解です。なお直近の決算短信で「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」の注記が記載されている会社は「継続疑義の注記」などの表現で記述している場合があります。
実質的な本社(本店)所在地を表示します。 登記上の本社所在地とは異なる場合があります。郵便番号は個別事業所の番号で記載している場合があります。
実質的な本社(本店)の電話番号を表示します。
最新時点の主要な営業所・支店・工場など事業所を示します。業種・業態によって収録項目が変わります。例えば、小売業は最新調査時点での店舗数・売場面積、銀行・証券は店舗数(ミニ店舗を除く)、鉄道会社は路線キロ数、海運会社は支配船腹量などを表示しています。
なお、スペースの都合によって省略している場合があります。
左から順にデータ年月、従業員数、平均年齢、平均給与を示します。
カッコ内に表示したデータ年月の次には、従業員数(就業人員数)を掲載しています。原則として直近の本決算もしくは第1または第2または第3四半期決算の期末のデータを掲載しています。合併会社の場合、決算期末の年月が表示されている場合は、存続会社の決算期末の従業員数を掲載しています。原則として有価証券報告書の記載基準に準拠しており、役員や臨時の従業員を含みませんが、一部例外もあります(会社法上の役員ではない執行役員は含んでいます)。「連」と表示されているのは連結ベースの従業員数、「単」と表示または特記がない場合は単独ベース、「子」は持株会社傘下の主要子会社(複数合算していることもある)の単独ベースの数字を掲載しています。原則単独従業員には他社への出向者を含んでいません。
つづけてのカッコ内は単独ベースでの従業員平均年齢で10進法で表記しています。
最後の右側に掲載しているのは単独ベースでの従業員の平均給与です。平均年齢、平均給与とも「子」となっている場合は従業員数と同様に主要子会社単独ベースです。原則、平均年収([年]と表示)で、税込み、残業料・諸手当・賞与を含んだ金額です(有価証券報告書記載基準によります)。年収についても、原則、本決算ベースですが、決算期を変更した会社は年換算した数値を掲載しています。平均年齢、給与は原則、本決算ベースです。
東経業種別時価総額順位は東洋経済新報社が独自に業種分類した「東洋経済業種分類」による業種名、続いて【株式】欄掲載の時価総額(発売前月下旬時点)の同一業種内順位(分子)と業種別社数(分母)を掲載しています。上場日が発売前月下旬以降の新規上場会社の場合は「―」としています。
東洋経済新報社が独自に業種分類した「東洋経済業種分類」による業種名、その業種内での時価総額順位を掲載しています。上場日が発売前月下旬以降の新規上場会社の場合は「―」としています。
証券欄には株式の状況を収録しています。
| 上 |
[上]は上場市場名で、地名は各証券取引所(金融商品取引所)を示します。 上場市場名の後の文字がカッコで囲まれている場合は、当該取引所が制度信用銘柄に採用していることを示します。 海外証券取引所の略称 |
|---|---|
| 幹 | [幹]は幹事証券会社(金融商品取引業者)を表します。そのうち(主)は主幹事、(副)は副幹事を示します。証券会社(金融商品取引業者)名は略称を用いています。なお、スペースの都合で省略している幹事証券(金融商品取引業者)があります。 |
| 名 | [名]は株式の株主名簿管理人です(特別口座の管理会社とは異なる場合があります)。「自社」は当該会社で行っているという意味です。 |
| 監 | [監]は会計監査人または直近決算の監査法人です。会計監査人の名称で「監査法人」「会計事務所」といった部分は省略しています(ただし、監査法人と会計事務所が同名の場合は会計事務所のみ省略せず記載しています)。また、会計監査人が複数にわたる場合は、原則、筆頭の会計監査人を表記し、末尾に「等」を付け加えています。個人名の場合も同様です。 |
主取引銀行の状況を収録しています。表示は『会社四季報』の調査ベースで、記載順序は会社の回答に準拠しています。中央銀行(日本銀行)は除き、銀行名は略称を用いています。なお、スペースの都合で省略している銀行があります。
インターネットで会社案内等を掲示している場合、その代表的なホームページアドレスを掲載しています。
会社の発行している株式関連のデータを収録しています。左から順に<日付><発行済み株式総数><時価総額><日経平均採用銘柄>を示します。
| 日付 | 四季報の各号発売の前々月末時点を示します。 |
|---|---|
| 発行済み株式総数 | 単位は千株(未満切り捨て)で表示しています。原則として優先株は除いています。合併会社の場合は、合併登記前でも株数の増加を含んで表示しています。 今号発売時点における1売買単位当たりの株式数を表しています。原則として単元株式数と一致しますが、単元株の引き下げを予定している会社の場合、単元株式数以下となる場合もあるのでご注意ください。 売買単位の右側に[貸借]という表記のある会社は、貸借銘柄であることを示します。また、[優待]という表記のある会社は、株主優待画面に株主優待制度の具体的内容が収録されていることを意味します。 |
| 時価総額 | 発売前月下旬時点のものです。当日終値(当日に売買不成立の場合は気配値、気配値なしの場合は直近の売買成立日の終値)に株価に対応する発行済株式数を掛けた額です。新規上場会社は「-」を表示しています。 |
| 225 | 「225」は日経平均採用銘柄であることを示します。 |
当該会社が発行する長期債券について、発行体の元本支払い能力の程度を示した記号を掲載しています。金融庁指定の格付機関のうち、主要四機関の、四季報発売前月下旬時点の格付を収録しています。[SP]はスタンダード&プアーズ、[M]はムーディーズ・ジャパン、[J]は日本格付研究所、[RI]は格付投資情報センターをそれぞれ表しています。
「格付」はもともと国・公共団体や企業が発行する債券について、発行者の元本支払い能力の程度を記号によって示した指標です。証券会社系の研究所等が発表している株価レーティングとは違い、株価の見通しや利益成長力を示すものではありません。株価は成長可能性を見るのに対し、格付は信用リスクを見ているという点で、性質が異なることに注意する必要があります。日本では企業が債券やCPを発行する際に、金融庁の指定格付機関の2つ以上から格付を取得しなければなりません。各機関の記号の見方等については以下をご参照ください。
なお、格付け符号の定義はムーディーズが長期格付け、他の3社は長期発行体格付けを示します。詳しくは各社のホームページをご覧ください。
○スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン(S&P): http://www.standardandpoors.com/home/jp/jp/
| AAA | 債務者がその金融債務を履行する能力は極めて高い |
|---|---|
| AA | 債務者がその金融債務を履行する能力は非常に高く、最上位の格付けとの差は小さい |
| A | 債務者がその金融債務を履行する能力は高いが、上位2つの格付けに比べ、事業環境や経済状況の悪化の影響をやや受けやすい |
| BBB | 債務者がその金融債務を履行する能力は適切であるが、事業環境や経済状況の悪化によって債務履行能力が低下する可能性がより高い |
| BB | 債務者は短期的により低い格付けの債務者ほど脆弱ではないが、高い不確実性や、事業環境、金融情勢、または経済状況の悪化に対する脆弱性を有しており、状況によってはその金融債務を期日通りに履行する能力が不十分となる可能性がある |
| B | 債務者は現時点ではその金融債務を履行する能力を有しているが、「BB」に格付けされた債務者よりも脆弱である。事業環境、金融情勢、または経済状況が悪化した場合には債務を履行する能力や意思が損なわれやすい |
| CCC | 債務者は現時点で脆弱であり、その金融債務の履行は、良好な事業環境、金融情勢、および経済状況に依存している |
| CC | 債務者は現時点で非常に脆弱である |
| R | 財務上の問題が理由で規制当局の監督下に置かれている債務者に付与される格付け |
| SD、D | 債務者の金融債務の少なくとも一部(格付けの有無を問わない)が履行されていないことを示す |
AAからCCCまでの格付けには、プラス(+)記号またはマイナス(-)記号が付与されることがあり、各格付けの中での相対的な強さを表します。(C)は格付けの見直しを必要とする特別な出来事または短期的なトレンドに焦点をあてた格付けの方向性に関するS&Pの意見を示すもので、(Cポ)は格上げの可能性、(Cネ)は格下げの可能性、(C不)は格上げ、格下げ、格付け据え置きのいずれの可能性もあることを示します。(ポ)、(ネ)、(安)、(不)、(N)は中期的に格付けがどの方向に動きそうかを示すもので、(ポ)=ポジティブは上方に向かう可能性、(ネ)=ネガティブは下方に向かう可能性、(安)=安定は安定的に推移しそうであること、(不)=方向性不確定は上方にも下方にも向かう可能性があること、(N)は方向性に意味がないことを表します。銀行や証券等についてはカウンターパーティ、生損保については保険財務力の格付けです。
○ムーディーズ・ジャパン(MDY):
http://www.moodys.co.jp/
| Aaa | 信用力が最も高いと判断され、信用リスクが最低水準にある債務に対する格付け |
|---|---|
| Aa | 信用力が高いと判断され、信用リスクが極めて低い債務に対する格付け |
| A | 中級の上位と判断され、信用リスクが低い債務に対する格付け |
| Baa | 中級と判断され、信用リスクが中程度であるがゆえ、一定の投機的な要素を含みうる債務に対する格付け |
| Ba | 投機的と判断され、相当の信用リスクがある債務に対する格付け |
| B | 投機的とみなされ、信用リスクが高いと判断される債務に対する格付け |
| Caa | 投機的で安全性が低いとみなされ、信用リスクが極めて高い債務に対する格付け |
| Ca | 非常に投機的であり、ディフォルトに陥っているか、あるいはそれに近い状態にあるが、一定の元利の回収が見込める債務に対する格付け |
| C | 最も格付けが低く、通常、ディフォルトに陥っており、元利の回収の見込みも極めて薄い債務に対する格付け |
AaからCaaまでの格付けに1、2、3の符号を付け、各格付けの中で1が上位、2が中位、3が下位にあることを示します。↑印は格上げの方向、↓印は格下げの方向、?印は方向未定で格付けを見直し中であること、(ポ)=ポジティブ、(ネ)=ネガティブ、(安)=安定的、(検)=検討中は格付けの中期的な方向性に関するムーディーズの意見を表します。銀行については長期預金、生損保については保険財務の格付け、金融持ち株会社に格付けが付与されていない場合は中核子会社の格付けです。
○日本格付研究所(JCR):
http://www.jcr.co.jp/
| AAA | 債務履行の確実性が最も高い |
|---|---|
| AA | 債務履行の確実性は非常に高い |
| A | 債務履行の確実性は高い |
| BBB | 債務履行の確実性は認められるが、上位等級に比べて、将来、債務履行の確実性が低下する可能性がある |
| BB | 債務履行に当面問題はないが、将来まで確実であるとは言えない |
| B | 債務履行の確実性に乏しく、懸念される要素がある |
| CCC | 現在においても不安な要素があり、債務不履行に陥る危険性がある |
| CC | 債務不履行に陥る危険性が高い |
| C | 債務不履行に陥る危険性が極めて高い |
| LD | 一部の債務について約定どおりの債務履行を行っていないが、その他の債務については約定どおりの債務履行を行っているとJCRが判断している |
| D | 実質的にすべての金融債務が債務不履行に陥っているとJCRが判断している |
AAからBまでの格付け記号には同一等級内での相対的位置を示すものとして、プラス(+)もしくはマイナス(-)の符号による区分があります。p印は公開情報に基づき当該債務者(発行体)の了解を得た上で付与する格付け、#印はクレジットモニター(見直し作業中)で、(ポ)はポジティブ、(ネ)はネガティブ、(不)は方向性不確定で見直し中であること、#印のない(ポ)、(ネ)、(安)、(不)、(複)=方向性複数は格付けが中期的にどの方向に動き得るかという見通しを示します。
○格付投資情報センター(R&I):
http://www.r-i.co.jp/jpn/
| AAA | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある |
|---|---|
| AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある |
| A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある |
| BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある |
| BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある |
| B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある |
| CCC | 信用力に重大な問題があり、金融債務が不履行に陥る懸念が強い |
| CC | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥る懸念が強い |
| D | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥っているとR&Iが判断する格付け |
AA格からCCC格までの格付けについて、上位格に近いものにプラス(+)、下位格に近いものにマイナス(-)の表示をすることがあります。op印は格付け関係者の依頼によらずR&Iの判断で付与した格付け、()内はレーティング・モニター(見直し作業中)の対象として格付けを見直していることを示し、格上げ方向、格下げ方向、方向は未定の3つがある。(ポ)=ポジティブ、(ネ)=ネガティブ、(安)=安定的は格付けの方向性を示し、中期的な方向性についてのR&Iの意見を表します。
号によって特集企画が組まれ、内容は更新されます。