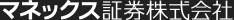チーフ・ストラテジスト 広木 隆が、実践的な株式投資戦略をご提供します。
広木 隆が投資戦略の考え方となる礎を執筆しているコラム広木隆の「新潮流」はこちらでお読みいただけます。
広木 隆 プロフィール Twitter(@TakashiHiroki)
疾風に勁草を知る
私の履歴書
日経新聞に月替わりで連載される「私の履歴書」。先々月はニトリの創業者・似鳥昭雄氏の「履歴書」が大きな反響を呼んだ。起業家や芸術家など、凡人の枠に収まらない波乱万丈な物語は誰が読んでも文句なしに面白い。それに対して、大企業に入社してトップに登りつめたひとの「履歴書」はつまらない。一応はいくつか修羅場をくぐってきたエピソードが披露されるのだが、所詮「サラリーマンの出世物語」だからである。
先月掲載されていた日立製作所相談役・川村隆氏の「履歴書」も、当初はそんな先入観を持って読んでいた。途中までは案の定といった感じだったが終盤に来て様相が変わった。子会社に出て6年、日立本体を離れていた川村さんに突然の復帰・社長就任要請が来る。リーマンショックで製造業として過去最悪の赤字を計上するなど、日立は「沈みゆく巨艦」だった。その日立の社長就任はまさに火中の栗を拾うような仕事。そこから川村さんの怒涛の改革が始まる。大なたを振るった事業リストラ、格下げ、増資決定、投資家との対話...苦境の連続だったがなんとか乗り切り、そして今、日立は甦った。
日立が立ち直った理由について、いくつもの論点があるだろう。だが、あえてひとつを挙げれば、「反省」ということに尽きる。川村さんをはじめ、改革を主導した首脳陣が、日立の「ダメなところ」を身をもって知り尽くしていたからこそ、「その逆をやった」ということである。
川村さんは、<私自身も「社長というイスに座って会社の顔として働く」ということを越えて、「経営のプロフェッショナル」の覚悟で事に臨むと心の中で確認した>と述べている。それは社内外の様々な行事に時間をとられすぎた副社長時代の反省からくるものであったという。大企業のお偉いさんともなると、名誉職であり仕事の大半が「セレモニー(儀式)」になってしまう。そして、日本企業の重役は、それに満足し、それをモチベーションとしている節がある。
川村さんの「履歴書」で、日立の工場長時代の話が書かれている。ハイキングに出かけた帰りに、首にタオルを巻いてバス停で待っていた。翌日、出社すると部下がやってきて「工場長があんなみっともない格好をしてはいけない」と注意を受けた。日立工場長といえば、日立市では市長と並ぶ「顔」のような存在なのだから、というわけである。
<日立工場に属する社員は5千人強、場内に出入りする業者を含めると常時7千人が働く大所帯。さらに社内教育機関の学生・職員もグループの一員であり、彼らが一堂に会する正月の賀詞交換会や秋の運動会はまことに壮観だった。運動会では工場長が壇上に登り、選手団の敬礼を受ける。「こんなに大勢の人の仕事や生活に責任を持つのか」と思うと、身が引き締まる思いだった。>(「私の履歴書」)
米英とは逆に傾いた振り子
当時の日立市はまさに企業城下町。病院から市内を走るバスまですべて日立の傘下にあった。老舗料亭がつぶれた時には、「君たちが利用してやらないからつぶれた。工場長の責任だ」とOBから叱責されたという。兎に角、日立市にあるものすべてに日立製作所の息がかかっていたと言っても過言ではない。
日立という会社は、地域のために病院を経営したりバスを走らせたり従業員のために運動会を催したりする。しかし、そこには「株主のため」という発想はまったく出てこない。良いか悪いかは別として、少なくとも米英型のコーポレートガバナンス(企業統治)の正反対である。日立製作所と言えば、日本を代表する企業だ。その姿がこれでは米英の投資家から、「日本企業は異質」と思われても不思議はない。要するに「振り子の針が振り切れる」ところまで米英の企業とは異質な反対方向に傾いてしまっていたのである。
その振り子の針が今度は反対の方向に振れ始めた。だからポテンシャルは大きい。「振り切れる」ところまで異質に傾いた振り子の針が、(良いか悪いか別として)米英流の株主重視の方向に振れ始めたのだから。このスイングバック(揺り戻し)は相当大きなものになるだろう。
「日本企業が変わる」ということの象徴例として挙げられるのがファナックの変貌ぶり。同社は投資家との対話に後ろ向きで株主還元も慎重とされてきたが、「物言う株主」として知られるサード・ポイントを率いるダニエル・ローブ氏から「不合理な資本構造」を指摘する書簡が送られたことなどもあってか、15年3月期から5年間、配当と自社株買いに利益の最大8割を充てる株主還元策を公表した。さらに株主との対話窓口「シェアホルダー・リレーションズ(SR)部」の設置を表明、社外取締役も増員した。
もう1社、半ば皮肉を込めて挙げられるのが三菱重工である。今でこそ10%のROEを中期経営目標に掲げる同社だが、約15年前、当時のトップが「ROEなんて眼中にない」というような趣旨の発言をして物議を醸した。三菱重工のROEを時系列で示したのがグラフ1である。これを見ると、長く1~3%台という低いROEが続いてきた。確かに「有言実行」だ。ROEなど眼中にない経営をしてきたことがよくわかる。

つまり、これだけ長い間、日本を代表する企業がROEや株主還元に無頓着だったわけで、それらが今から一様に株主重視に舵を切り始めたとすれば、このスイングバック(揺り戻し)が相当大きなものになるという主張にも同意してもらえるだろう。
日本企業は本当に変わるか
6月は株主総会シーズンだ。東証が定めた企業統治指針(コーポレートガバナンス・コード)の適用開始もあって、これまでにないほど「日本企業が変わる」という機運が内外で高まっている。
しかし、「変わる」「変える」「変革」というものは、そうそう一朝一夕にいくような甘いものではあるまい。5月22日付けレポート「明明白白なこと」 で述べた通り、この相場の本質は偉大なる「官製相場」であり、企業改革の機運すら、政府主導のシナリオに沿った「官製企業改革」である。ROEの向上も、株主還元策の強化も、企業側から自発的に出たものは限定的だろう。大半は産業界全体の「ムード」に流されているだけだ。スティール・パートナーズやTCIなど元祖「物言う株主」が日本に上陸したのは10年も前のことではない。その時は買収防衛策を検討したりして断固として対話を拒んだくせに、政府から言われると手の平を返したように従順に従う。
コーポレートガバナンス改革にしても、現在はまだ形式的な域を出ない。社外取締役を増やせば経営が劇的に良くなるか?そんなわけがない。この点については著書「ROE投資術」でも述べているけれど、このストラテジーレポートでもまた別の機会に触れたいと思う。
変革の必要性に対する自覚
では、どういう企業が本当に「変わる」のか?それは企業自ら真に変革の必要性を自覚した企業である。平易な言葉で言えば、「変わらなければ潰れてしまう」くらいの危機感を持った企業である。
盤根錯節に遭わずんば何をもって利器を分かたんや
という言葉がある。苦境に立ってはじめて、ひとやものの真価が判別できるということだ。本稿で引いてきた例で言えば、日立などはその典型例だろう。以下は、増資への理解を得るため、川村さんたちが海外投資家に説明して回ったときの「私の履歴書」からである。
<激しい叱責と議論に何日も身をさらして精神的にかなり応えたが、こちらの発するメッセージは一つしかない。「今後はしっかり改革して株主の期待に応えるので、今回ばかりは増資を応援してほしい」というものだ。散々批判しながらも、最後に「増資は引き受ける」と言ってくれる投資家もいて、そんな時は目頭が熱くなった。
この増資行脚の最後にニューヨークと東京やその他地域をまわっているチームを結んで電話会議を行い、関係者の苦労をねぎらうとともに自分の考えを述べた。「皆さん、本当にありがとう。私は日立に入ってからいろいろなものを売ってきたが、日立の製品は品質や性能、納期を保証し、守れなければ罰金を支払うので、お客様は安心して買える。だが株式は違う。配当も株価も保証はない。この先どうなるかわからない株を日立を信じて買ってくれた投資家の方々の期待に応えなくてはならない」という趣旨だった。>
こういう想いをしたひとたちが経営する企業の「株主重視」は本物だと思う。
盤根錯節に逢わずんば何をもって利器を分かたんや
別の言葉では、
疾風に勁草を知る
というのもある。暴風に吹かれてはじめて、倒れない強い草がわかるのだ。
富士フイルムは「勁草」の代表例だろう。なにしろ、自分たちの社名に記した「写真フィルム」という事業そのものが消えてしまったのだから。急速なデジタル化の波が、銀塩系写真フィルム市場を消滅させた。誰の目にも明らかな危機だったからこそ、危機感が全社で共有できた。2006年に、それまでの「富士写真フイルム」という社名から"写真"の看板を下ろし、持ち株会社の「富士フイルムホールディングス」を設立。傘下に「富士フイルム」と「富士ゼロックス」の2大事業会社を持つ形にシフトした。社名変更は、写真以外の成長事業に大きく舵を切る決意表明だった。以降、事業構造の大転換を進めた結果、より強い会社に、以前にも増して日本を代表する優良企業に生まれ変わったのは誰もが知るところだ。
かつて日本企業は大きな危機に直面するたびに、危機感をバネに苦境を克服して成長してきた。1960年代の貿易自由化、70年代のオイルショック、90年代後半の金融危機。阪神淡路大震災に東日本大震災という危機もあった。ひところ前は「6重苦」としきりに言われたが、最近の「アベノミクス」「円高の是正」で一気に危機感が薄れていないか。円安頼みの業績回復に安住していては、リーマンショック前、新興国の台頭で起きたグローバル景気に便乗して「好業績」を謳歌したのと変わらない。
企業自ら危機感を持ち、改革に取り組んでいる企業こそ「勁草」と成り得るのである。その意味ではソニーやシャープ、そして最近では東芝に吹いている疾風が、利器を分かつことに期待している。
(※)印刷用PDFはこちらよりダウンロードいただけます。