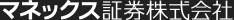チーフ・ストラテジスト 広木 隆が、実践的な株式投資戦略をご提供します。
広木 隆が投資戦略の考え方となる礎を執筆しているコラム広木隆の「新潮流」はこちらでお読みいただけます。
広木 隆 プロフィール Twitter(@TakashiHiroki)
2016年以降の経済・市場展望 PART1 米国株式市場と米国金利
「2016年」ではなく「2016年以降」としたのは、より中長期の見通しにも一部言及するからである。まずPART1では米国の利上げで株式市場と長期金利はどう動くのか見通しを述べる。米国の利上げとそれを受けた各市場の反応は2016年、最大のテーマと言っても過言ではないだろう。
1. バリュエーションの低下
相当高い確信度を持って言えることは、株式市場のバリュエーションは低下する(少なくとも上がらない)ということである。教科書的に言えば、例えばPER(株価収益率)は割引率(資本還元率)の逆数で、割引率は安全資産の利子率と株式リスクプレミアムで構成されるから、利上げは安全資産の利子率上昇を通じてバリュエーションを押し下げる。そして、グラフ1に示したように、過去、実際のマーケットでもバリュエーションの低下が確認された。表1にまとめた通り、利上げ期間を通じてPERは平均で3倍低下する。率にすると9%低下した。


バリュエーションは低下するものの、利上げ開始で米国株相場が腰折れた例はない。利上げ期間を通じてS&P500は約2割上昇した。ピークを打つまでの期間は28カ月、つまり利上げ開始から平均すると2年以上は上昇相場が続いたということだ。利上げするということは基本的に景気が強いということだから企業収益の面では概して好環境だったと言える。過去の利上げ期間を通じて企業の業績は平均して3割拡大した。株価が業績の伸びをそのままトレースしたら3割上がっていたところが、2割の上昇率にとどまったということは、バリュエーションの押し下げ分がそっくり株価の重石となったということである。そういう意味では利上げは(教科書通り)株価にマイナスの影響を与えたのである。過去、利上げ期間中にもかかわらず株価が上がったのは利益が大幅に伸びたからである。
過去と比べて今の米国企業は稼ぐ力が落ちている。トムソン・ロイター調べによると主要企業の7-9月期の1株当たり利益は0.8%の減益となった。原油安でエネルギー業種が大幅減益となったほか、ドル高がグローバル企業の業績の重石となった。四半期決算で減益となるのはリーマン危機後に景気後退期に入った09年7-9月期以来、6年ぶりだ。
しかし、減益決算は6年ぶりとは言え、これまで四半期決算のたびに、「今回ばかりは減益が免れないか」と言われ続けて、最終着地はかろうじて増益をキープしてきた。増益と言っても、「減益ではない」という程度。ほぼ横ばいで利益成長がない状態が続いてきた。
それもそのはずだ。トップライン、つまり売上高が伸びていないからである。低成長時代に売上高を伸ばすのは至難の業だ。米国企業はコスト削減と自社株買いでボトムライン(EPS)を伸ばしてきた。7-9月期の1株当たり利益は0.8%の減益となったと述べたが、売上高は4.4%も減収である。
2016年は米国企業のEPSは8.7%伸びることが見込まれている。しかし、そんな「予測」はあってないようなものである。ちなみに7-9月期の1株当たり利益は0.8%の減益となったが、今年の1月1日時点では7.4%の増益予想だった。10~12月期1株当たり利益は3.1%の減益予想だが、今年の1月1日時点では12.9%の増益予想だった。このように米国企業の業績は日を追うごとに下方修正されるのが今や当たり前の状況になっている。
2016年も米国企業にとって業績のドライバーとなるような要因はなく低成長が続くだろう。そこに利上げでバリュエーションに低下圧力がかかるとなれば、米国株は上昇しない。よくて横ばいだろう。無論、PERがすぐに低下するわけではない。政策金利が相応に引き上げられて、過去平均3倍程度下がったという事実に照らせば、しばらくバリュエーションは現状のままにとどまる可能性もある。但し、それは非常に危うい均衡に見える。
トムソン・ロイターの推計によれば、向こう1年先の予想利益ベースのS&P500のPERは16.9倍であり、過去平均対比は高いものの、それほど割高というわけではない。しかし、エール大学のロバート・シラー教授が提唱するCAPE(景気循環調整後PE)で測った米国株のバリュエーションは相当危険水域に達している。11月10日付レポート「上放れの並び赤」で紹介したように、PERのもとになるEPSは特別損益などの影響を受けやすいだけでなく、1期だけの業績であるため、たまたま好景気で高い利益が出たとか、その反対に不景気で利益が落ち込んだり変動が激しい。CAPEは過去10年間のインフレ調整後平均利益を使うことで、景気変動の影響を除去したバリュエーション指標となっている。

過去135年間で、このシラーP/Eレシオが25倍を超えたのは、3回しかない。1929年の大恐慌の直前の株価バブルの時期と2000年のIT株バブル(45倍と米国株市場が最もバブった時期)、そして2008年、サブプライムローン・バブルの時期である。その後、バブル崩壊で株式市場が大暴落となったことは説明不要だろう。
そして今またCAPEは25倍台に上昇している。08年9月のリーマンショックで、過去平均の16.6を下回り15倍台に下がった後、上昇を続け、現在は26倍である。つまり、景気循環を考慮した利益水準は現在の株価をジャスティファイできないということだ。現在の株価水準が、こうした「危うい均衡」にあるなか、原理原則からすればバリュエーションを押し下げる力がかかる利上げを迎えるのだということを、よく認識しておく必要があるだろう。
2. 利上げのペース
米国企業業績の伸び鈍化、バリュエーションの低下が予見されるなか、鍵を握るのは利上げのペースがどうなるか、ということである。これについては、「この12月から利上げが開始され、その後2016年は四半期毎に25bpsずつFF金利誘導目標が引き上げられる」というのが市場のメインシナリオと考えて良いだろう。ざっくり言って、今後1年で1%、政策金利が上がる、という見通しである。
なぜこの見通しがメインシナリオとなったかと言えば、前回のFOMC議事要旨の冒頭で、均衡実質金利(equilibrium real interest rate)に関する議論が記述されていたからだ。FOMCスタッフは様々な手法による推計を示し、均衡実質金利は(1)金融危機後にマイナス領域まで低下した、(2)その後回復したがゼロ近傍にあり、過去の景気拡大期に比べて相当低い、(3)米国に限らず多くの先進国では、過去四半世紀には実質短期金利がゼロ近傍にあった、(4)TFPと労働力人口の成長率が改善しなければ、均衡実質金利は金融危機前に比べて低位に止まる、といった点を説明したという。
端的に言って、均衡実質金利は政策金利の目標となり得るものだ。FF金利は名目の値だから、「均衡実質金利+インフレ率」=「目標FF金利」と考えていいだろう。そうすると、均衡実質金利が現在ゼロ近傍、FEDが見ているインフレ率の指標であるコアPCE(総合個人消費支出)デフレーターは1%台前半であるから、当面の目標FF金利も1%台前半となるはずだ。これが、四半期毎に25bpsずつFF金利誘導目標が引き上げられて、今後1年で1%、政策金利が上がる、という見通しの根拠である。
3. コナンドラム再び - 長期金利は上がらない
もうお分かりだろうが、今後の利上げのペースと水準は、インフレがどうなるかでほぼ決まると言っていい。仮にFEDがターゲットとするインフレ率2%が達成されるとしても、均衡実質金利が現在ゼロ近傍である状況が変わらなければ - そしてそれは一朝一夕に変わるものでもないため - FF金利もせいぜい2%台前半までしか上がりようがないということだ。
現在、FOMCメンバーの長期的なFF金利の見通しは中心値で3.5%だが、これは時間の経過とともに下がってきている。次回、12月会合で示されるドットチャートでも再び下がるだろう。理由は前段で述べた通りである。利上げ決定と同時に先行きの政策金利の見通しを下方修正するだろう。こうした状況では長期金利は上がりようがない。イールドカーブはフラットニングを一層強めるだろう。

これは今年5月に書いたレポート「米国の長期金利は上昇するか」の結論を撤回するものである。前回の利上げ時(2004年~)には度重なる利上げにもかかわらず、長期金利が上昇せず、その状況を当時のFRB議長アラン・グリーンスパンは「Conundrum(コナンドラム:謎)だ」と呼んだ。「米国の長期金利は上昇するか」のレポートでは、当時長期金利が上がらなかったのは、タームプレミアムが剥落し大幅に低下したからであるとのNY連銀の分析を紹介した。そして、今はマイナスの領域にまでタームプレミアムが下がっており、低下余地が限られる、すなわちタームプレミアムはこれ以上、下がりようがないのだから後は上がるだけ、少なくとも短期金利上昇に合わせて長期金利は上がるだろうというのが結論だった。レポートの最後で、<今度、FRBが利上げに動くとき、イエレン議長はグリーンスパンの台詞、「Conundrum(謎)」を繰り返すことはないだろう>と書いたけど、撤回させていただく。
前回の利上げ時、タームプレミアムを食い尽くしたのは米国債に対する中国からの旺盛な投資需要だった。当時は中国が貿易で稼いだドル紙幣が米国債に振り替わって中国の外貨準備を構成するという構図だった。ところが今や180度、正反対の状況にある。中国経済の構造変化もあって、中国はもはや貿易で稼げなくなりつつある。外貨準備は減少の一途だ。中国は米国債を売却しているとの憶測も絶えない。しかし、それが事実だとしても米国金利は上がらない。中国に絡む需給だけで米国債市場という大きなマーケットの需給を読み解くのは無理があるだろう。

話をもう一度、タームプレミアムに戻そう。5月のレポートで米国金利が今度は上がるだろうと予想したのは、タームプレミアムがマイナス領域まで下がっており、低下余地が限られる、これ以上、下がりようがないのだから、というのが根拠だった。しかし、その後、欧州はマイナス金利が拡大し、日本までもドル資金調達にプレミアムがついていることから短期国債利回りがマイナスで推移している。もはや、マイナス金利の世界が常態化している。
異常なことが平気で起こる時代になった。これが僕が見方を変えた理由である(いまさら感満載だが)。
異常なことと言えば、スワップスプレッドのマイナスが拡大している。米国債よりスワップ金利のほうが低いのだ。アメリカという国家の債務より、カウンターパーティ・リスクのあるスワップ契約のほうが信用力が高いといわんばかりだ。
異常なことの常態化 - それはすなわち、言い古された感のある「ニューノーマル」という概念がまだ厳然と続いているということなのだろう。「ニューノーマル」と表裏一体で語られることの多い「セキュラー・スタグネーション(長期停滞論)」。この理論の提唱者であるローレンス・サマーズ の主張を要約したポール・クルーグマンのニューヨークタイムズ紙への寄稿がある。もう2年も前に書かれたものだが、奇妙なほど現在にフィットしている。<彼は、このような状況(=均衡金利がマイナスの状況)では通常の経済政策のルールは通用しない、ということも指摘している。僕が好んで使っている表現で言えば、美徳は悪徳になり、慎みは愚行になるのである。貯蓄は倹約のパラドックスのために経済を停滞させ、さらに投資も停滞させる。債務や赤字を軽減しようとすることは、不況をさらに悪化させる>(Secular Stagnation, Coalmines, Bubbles, and Larry Summers; NOVEMBER 16, 2013)
マイナス金利の世界では、普通の世界の「常識」が「非常識」になる。だから - タームプレミアムだってマイナスが常態化しても、もはや不思議でもなんでもない。米国の長期金利は、少なくとも利上げ開始からしばらくは大きく上昇することはないだろう。
PART2 では為替の見通しと米国経済のより根本的なイシューについて述べる。頭出ししておくと、今後の利上げはインフレが鍵と書いたが、そのインフレは弱いままだろう。原油価格云々の話ではない。原油等コモディティ市況が軟調だというのは、インフレ(の一部)が弱いということでトートロージー(自己循環論法:同じことの言い換え)に過ぎない。インフレが高まらないのは賃金が伸びないからで、それはここ数年のことではない。もっと長期かつ本質的な問題がそこにある。「21世紀の資本論」もしくは「21世紀の産業革命」と言うべき問題である。
(※)印刷用PDFはこちらよりダウンロードいただけます。