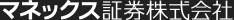チーフ・ストラテジスト 広木 隆が、実践的な株式投資戦略をご提供します。
広木 隆が投資戦略の考え方となる礎を執筆しているコラム広木隆の「新潮流」はこちらでお読みいただけます。
広木 隆 プロフィール Twitter(@TakashiHiroki)
日経平均の21年ぶり高値に思うこと
門松は 冥土の旅の一里塚 めでたくもあり めでたくもなし
一休さんの作とされるこの歌は、寄席の大喜利のお題によく使われる。下の句の「めでたくもあり めでたくもなし」につなげる上の句を作れというお題である。例えば、こんな感じだ。
日本株 21年ぶり高値 めでたくもあり めでたくもなし
日経平均が2万1000円を超えてきた。1996年以来、21年ぶりの水準である。「めでたくもあり めでたくもなし」といったところだ。なぜ素直に喜べないのか?「21年ぶり」というのが悲しいのである。なぜなら、ただ昔の水準を回復しただけであるからだ。日本以外、米国をはじめ諸外国の株価は史上最高値圏にある。〇年ぶりとか言っているのは日本だけだ。海外市場はいまだかつてない高みに登りつめている。かたや、こちらはバブル崩壊の傷跡が残る時代に戻っただけだ。あまりにも差があり過ぎるではないか。
21年ぶりの株価に戻ったという事実をそのまま受け止めれば、この21年間、我が国の経済と企業は何をしていたのかということになる。この間、米国でもITバブル崩壊やリーマンショックといった株価の暴落局面を経験した。しかし、その度に数年でその暴落前の水準を取り戻し、再び上昇基調に回帰していっている。それが本来の株式市場の趨勢なのだ。
米国のS&P500はリーマンショックの前年2007年10月にそれまでの史上最高値1565ポイントをつけた。そこをピークに株価は下落、翌年のリーマンショックで奈落の底に沈んだ。しかし、2013年4月にはリーマンショック前の高値1565ポイントを回復している。高値つかみをしてその直後、暴落に見舞われたとしても、わずか5年あまりで取り戻したことになる。
ブルームバーグは先日、<強気相場ピークでも「米国株は買い」の理由>という記事を掲載した。
<約10年前に米S&P500種株価指数に資金を投じた場合、途中その半分以上が吹き飛ぶ瞬間もあっただろう。しかし、トータルリターンを考えれば、あなたの投資は倍増したはずだ。
配当再投資分を計算に入れると、2007年の終値ベースのピークを付けた同年10月9日から現在までのS&P500種のリターンはプラス98%。09年3月の安値では一時マイナス55%となったが、その分を埋め合わせてさらに上昇し、過去10年の年間リターンは7%を上回る。>

我が国の上場企業の業績は最高益が見込まれている。利益が最高なら株価も最高であってよい。そうなってないのは、昔の株価が高過ぎたからにほかならない。
1996年度の東証1部の時価総額は約300兆円だった。今は600兆円を超えているから倍以上になった。この間、上場企業の数も増えた。96年当時、東証1部の上場企業数は約1300社。今は2030社だから5割以上増えた。確かに「東京市場」は大きくなった。しかし、東証株価指数(TOPIX)の水準が96年当時と比較してたいして変わっていないことから明らかなように、株価は上昇していない。TOPIXは時価総額をベースにした指数だが、増資などがあった場合、基準時価総額を調整することで株価の変化だけを追う構造になっている。
一方、利益はどうか。今年度の予想業績を96年度と比較すると、経常利益は3.6倍に、純利益は6倍に増える見込みである。利益が何倍にも増えて、株価が当時と変わらないというのは、当時のバリュエーションが滅茶苦茶だったということである。80年代後半のバブル時代には、PERのようなバリュエーションはまったく機能しなかった。だが、バブルが崩れた後、90年代もまだ不良債権処理などの減損が続き、最終利益は低迷し続けた。それに比べて株価の調整がじゅうぶんではなかったため、株価尺度としてほとんど意味をなさないようなバリュエーションが続いたのである。
まあ、過去を嘆いてもしかたない。このブログで書いたように、実は日本株はすでにバブルの清算を終えて極めてフェアな(妥当な)株価と利益の関係になっている。下のグラフからも、2010年ごろから利益の伸びに沿って時価総額が拡大しているのが見て取れる。それ以前、特に1990年代は利益水準と時価総額が乖離している。

昭和末期のバブルが起きる前、80年代前半の東証1部時価総額は、東証1部上場企業の経常利益の約10倍だった。つまり経常利益ベースのPER10倍ということである。今は概ねその水準に戻っている。ここからは利益の伸びに沿って株価が上昇していくだろう。非常にクリアな株価形成メカニズムが機能する市場になったと言える。
足元の動きについて、日経平均2万1000円をトリガーとするリンク債のヘッジ外しやコールオプションの売りに対する先物の買いヘッジなど、需給が主な要因だという論調が一部にある。こうした「需給」というのは「結果」であって、「要因」ではない、というのが僕の持論である。
シンプルな話、ではまたこの水準からショートが振れるか?衆院選での与党勝利の観測、それに続く4-9月期決算で業績上方修正の可能性、米国ではFRB議長人事、税制改革への期待、12月利上げ観測。こうした株高・円安・リスクオン材料が年末まで続く環境ではまた担がれて踏まされるのがオチだろう。売り方不利で売りがしぼむ。結果として上値は重くならないはずだ。
従前から述べている「日経平均の年末予想値:2万2000円」の蓋然性が高まった。いや、もっと上振れする可能性も出てきたように思う。
死角はないか?あるとすれば、「慢心」だろう。
ただ、その点については、大半のひとは半信半疑で、相場に対する弱気論や警戒論が世の中にあふれているから大丈夫だろう。「まだはもうなり、もうはまだなり」だが、「まだ」先は長いと思う。
あのウォーレン・バフェットも絶大な信頼を寄せる投資の賢人、ハワード・マークス(オークツリー・キャピタル共同創設者)が、現在の強気相場を「野球で言えば8回」と警鐘を鳴らしたのは7月下旬のことだ。このエピソードは先日、日経新聞のコラムでも紹介されたからご存じのかたもおられるだろう。
しかし、野球の「イニング」は、アメリカン・フットボールやバスケットボールの「クオーター」、サッカーやラグビーの「ハーフ」のようにプレイの時間が決められているものではない。
ハワード・マークスもその点をじゅうぶんに理解しているから「野球のイニング」をたとえに使ったのであろう。彼が述べた言葉は正確にはこうである。
「野球で言えばわれわれは8回まで来ているような感じがする。しかし、私にはこの試合がどれだけ長く続くかまったくわからない」
【お知らせ】「メールマガジン新潮流」(ご登録は無料です。)
チーフ・ストラテジスト広木 隆の<今週の相場展望>とコラム「新潮流」とチーフ・アナリスト大槻 奈那が金融市場でのさまざまな出来事を女性目線で発信する「アナリスト夜話」などを毎週原則月曜日に配信します。メールマガジンのご登録はこちらから
(※)印刷用PDFはこちらよりダウンロードいただけます。