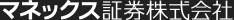チーフ・ストラテジスト 広木 隆が、実践的な株式投資戦略をご提供します。
広木 隆が投資戦略の考え方となる礎を執筆しているコラム広木隆の「新潮流」はこちらでお読みいただけます。
広木 隆 プロフィール Twitter(@TakashiHiroki)
「日経平均3万円への道」アップデート 2018年5月
3万円の達成時期は後ろ倒しとなろうが悲観シナリオはかなり後退
前回のアップデートでは、日経平均が3万円に到達するという従来の基本観を維持したうえで、ただし3万円到達時期が1年後ろ倒しの2019年度末(2020/3月)というシナリオをもうひとつ提示した。その理由として、グローバル経済や企業業績などファンダメンタルズは良好だが、市場のセンチメントが極端に悪化したからだと述べた。いったんマーケットが大きく崩れるとセンチメントの回復には相応の時間を要する。今後、株価が戻るにせよ、発射台が下がってしまっている以上、当初3万円の到達時期と想定していた2018年度末(2019/3月)より後ずれする可能性が高まったとしたのであった。
さて、それから2カ月が経過した。もう一度、アップデートをしておこう。その後の相場の推移だが、レポートで述べた通りの展開となっている。僕は「3月中にも一番底が入ると見ている(節分天井、彼岸底だ)」と述べたが、果たして日経平均は3月のお彼岸過ぎに底打ちし、その安値から2000円戻している。1月高値からの下げ幅の半値戻しは達成したので、「半値戻しは全値戻し」の格言に倣えば、早晩高値に戻るだろう。
僕は、「円高もここまで」と述べてきた。ドル円もそのタイミングで底をつけて、一時1ドル110円台まで戻した。それもあって、決算発表前には減益の懸念まで出ていた今期の業績だが、おそらく7%増益程度でまとまるだろう。これも当初の見通し通りである。日経平均のEPSは1700円台。あとはセンチメントの回復≒バリュエーションの回復を待つだけである。
北朝鮮情勢の緊張緩和や、米中の貿易戦争が報復合戦にエスカレートするような展開にならなかったことも市場の過度な悲観論を後退させている。
そもそも今回の株価急落を引き起こしたとされる、米国の雇用統計での賃金上昇、それを契機とする長期金利の急騰などは本質的な株価の下げ要因でないことがわかってきた。これも僕が当初から主張していることなのだが、あまり「当たった、当たった」と自慢するのも大人げないのでこれでやめておく。肝心の「3万円はどうなったんだ?」と混ぜっ返されてもたまらないので。
兎に角、平均時給の急上昇は統計上のテクニカルな要因による一時的なもので、その後、平均時給は伸び悩んでいる。それにもかかわらず米国10年債利回りは結局3%の大台をつけた。賃金上昇⇒インフレ期待上昇⇒金利上昇、というプロセスではない。
また金利が上がっても米国の株価は大崩れしていない。取引時間中に3%をつけた4/24は400ドルを超える下げとなったが「キャタピラーショック」の日だったから、どこまで金利上昇を嫌気したかわからない。そして明示的なのが10年債利回りが3%をつけて終わった4/25、ダウ平均は59ドル高と上昇したことだ。一時は200ドル安まであって切り返した。つまり、「長期金利3%」を乗り越えての上昇だ。金利上昇という材料を消化したと言える。たしかにダウは上値も重いが200日移動平均を下回らない。
要は慣れの問題だと言い続けてきた。これまでの適温相場では、金利も賃金も物価も原材料も、何もかも「上がらない」のが当たり前だった。しかし、これだけ長く景気回復が続いて来れば、「上がるのが当たり前」の世界になる。それが当然なのであるから、慣れるかどうかである。
相場もまた然りで、3%の長期金利も常態化すればそれに慣れる。急上昇がなければよい。米国株は、企業業績が伸びる分だけ株価は上がるだろう。バリュエーションの拡大を伴わず、マイルドな上昇となるだろう。日本株は、業績増に加えてバリュエーションの修正が期待できる。金利が上昇する見通しがないので、なおさらバリュエーションの上昇は(少なくとも米国に比べて)正当化されるだろう。
前回からアップデートで、ひとつ修正が必要な点がある。従来述べてきた「グローバル経済や企業業績などファンダメンタルズは良好だが、市場のセンチメントが極端に悪化した」という箇所の、「グローバル経済は良好」というところが怪しくなってきた。足元、各国・地域で景況感の悪化が目立つ。ドイツのIfo経済研究所が発表した4月のドイツIfo企業景況感指数は102.1と、3月の103.3から悪化した。5カ月連続の悪化である。ユーロ圏のCPI(消費者物価指数)の前年比は1%台前半で伸び悩み、ECBが目標とする「2%近く」には届かないままだ。一時は早期に金融政策正常化へ向かう観測が台頭し、それがユーロ高を示現させてきたが、足元ではむしろ緩和継続の見方が増えている。英国でも4月の製造業PMI(購買担当者景気指数)が低下、2016年11月以来の低水準となり、イングランド銀行の利上げが一段と遠のいた。英ポンドは過去1年以上、対ドルで上昇してきたが直近では明らかにトレンドが下方に転換している。
日本でも、3月の日銀全国企業短期経済観測調査(短観)で、大企業製造業の業況判断DIが8四半期(2年)ぶりに悪化した。そのほか景気動向指数が大幅に下振れたあとも戻りが鈍く、街角景気(景気ウォッチャー調査)なども弱含んでいる。こうした景況感の悪化もあって一時は執拗に喧伝された日銀の早期金融緩和縮小観測も鳴りを潜めた。ダメ押しとなったのが、日銀が4月末に公表した「経済・物価情勢の展望(展望リポート)」だ。これまで「2019年度ごろ」としていた2%の物価目標の達成時期に関する文言を削除した。黒田総裁は「(物価目標2%の達成時期は)達成期限ではなく、見通しであることを明確にするため、記述の仕方を見直すこととした」と述べたが、市場は日銀の出口政策が一段と遠のいたと受け止めた。こうした各国・地域の景況感の悪化⇒金融政策の緩和的状況維持というスタンスに対して、米国ではFRBによる継続的な利上げシナリオがこの先も確実視されている。これが一時1ドル110円台をつけたドル独歩高の基本的な背景であろう。
ところがその米国でさえ、雇用統計では雇用者数の伸びが市場の予想を下回った。前述の通り、賃金上昇も加速していない。全米サプライマネジメント協会(ISM)が発表した4月の製造業景況感指数は前月から2.0ポイント低下して57.3だった。2カ月連続の低下とはいえ、依然50を大きく上回る高水準であり、かつ重要項目の「新規受注」の低下幅はわずか0.7ポイントで、極めて良好であることを示す60台を維持していることなどから、すぐに米国景気が変調をきたすような懸念はない。しかし、同じく重要項目の「雇用」は2月の59.7をピークに3月は57.3、4月は54.2と2カ月続けて大きな落ち込みとなった。昨年の8月と10月につけた59.8が今回の回復局面のピークであり、雇用状況はピークアウトしつつあるように見える。こうしたことから直近は、連邦準備理事会(FRB)は利上げを急がないとの見方が浮上している。
昨年までの日米欧に中国を加えた、「全世界同時好況」ともいう状況が極めて異例であり、さすがにそうした状況が長くは続かないだろう。しかし、これでグローバル景気が息切れするかはまだわからない。確かにスローダウンはしているが、リセッションには至らず、「ソフトパッチ(ぬかるみ)」もしくは「踊り場」というような状況ではないかと考えている。
そして、それが株式相場にとって好都合となる場合もある。米国の金利上昇が懸念されている状況では、スローダウン、ソフトパッチはむしろ歓迎されるべきではないか。

【お知らせ】「メールマガジン新潮流」(ご登録は無料です。)
チーフ・ストラテジスト広木 隆の<今週の相場展望>とコラム「新潮流」とチーフ・アナリスト大槻 奈那が金融市場でのさまざまな出来事を女性目線で発信する「アナリスト夜話」などを毎週原則月曜日に配信します。メールマガジンのご登録はこちらから
(※)印刷用PDFはこちらよりダウンロードいただけます。