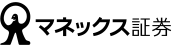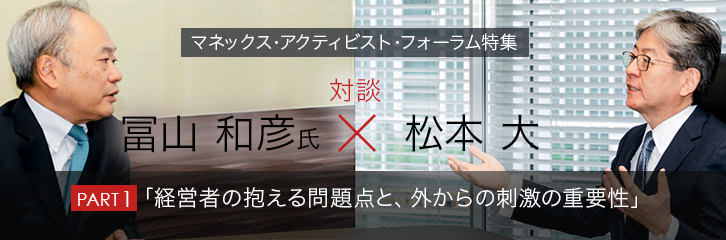
マネックス証券では、「マネックス・アクティビスト・フォーラム」と題して、個人投資家が積極的に投資先企業へ意見を発信していくことを応援する取り組みを行っています。今回は、パナソニックや東京電力ホールディングスの社外取締役を務める冨山和彦氏と、マネックス証券代表取締役会長松本大が対談いたしました。PART1のテーマは、「経営者の抱える問題点と、外からの刺激の重要性」です。
マネックス証券では、「マネックス・アクティビスト・フォーラム」と題して、個人投資家が積極的に投資先企業へ意見を発信していくことを応援する取り組みを行っています。今回は、パナソニックや東京電力ホールディングスの社外取締役を務める冨山和彦氏と、マネックス証券代表取締役会長松本大が対談いたしました。PART1のテーマは、「経営者の抱える問題点と、外からの刺激の重要性」です。

株式会社経営共創基盤(IGPI)
代表取締役CEO
冨山 和彦 氏
東京大学法学部卒、スタンフォード大学経営学修士(MBA)、司法試験合格。ボストンコンサルティンググループ、コーポレイトディレクション代表取締役を経て、2003年に(株)産業再生機構設立時に参画しCOOに就任。解散後、IGPIを設立、数多くの企業の経営改革や成長支援に携わり、現在に至る。パナソニック(株)社外取締役、東京電力ホールディングス(株)社外取締役。経済同友会政策審議会委員長。財務省財政制度等審議会委員、財政投融資に関する基本問題検討会委員、内閣府税制調査会特別委員、内閣官房まち・ひと・しごと創生会議有識者、内閣府総合科学技術・イノベーション会議基本計画専門調査会委員、文部科学省中教審実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化に関する特別部会委員、金融庁スチュワードシップ・コードおよびコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議委員、経済産業省産業構造審議会新産業構造部会委員他。

マネックス証券株式会社
代表取締役会長
松本 大
1963年埼玉県生まれ。1987年東京大学法学部卒業後、ソロモン・ブラザーズを経て、ゴールドマン・サックスに勤務。1994年、30歳で当時同社最年少ゼネラル・パートナー(共同経営者)に就任。1999年、ソニー株式会社との共同出資でマネックス証券株式会社を設立。2004年にはマネックスグループ株式会社を設立し、以来CEOを務める。マネックスグループは、個人向けを中心とするオンライン証券子会社であるマネックス証券(日本)、TradeStation証券(米国)・マネックスBOOM証券(香港)などを有するグローバルなオンライン金融グループである。株式会社東京証券取引所の社外取締役を2008年から2013年まで務めたほか、数社の上場企業の社外取締役を歴任。現在、米マスターカード、株式会社ユーザベースの社外取締役も務める。
- 冨山氏×松本対談 PART1
- 冨山氏×松本対談 PART2
サマリー
- 環境が大きく振れやすい昨今において、イノベーションに対応する立場にある経営者が持つ役割は大きい
- 経営者(内)と社外取締役(外)がビジョンを共有すべき
- 社外取締役・株主のクオリティーを上げていかなければならない

経営者の抱える問題点
松本:
本日は、エンゲージメントをテーマに、日本におけるコーポレート・ガバナンス改革や、フィデューシャリー・デューティーの概念、株主が企業の経営にもっと関わるべきといった点についてお話しを伺いたいと思います。まず、企業のコーポレート・ガバナンスが、企業の成績、あるいは企業が生み出す富やサービスに、どのように関係があると、冨山さんは考えていますか。
冨山:
組織内の最高権力者である経営者が、難しい環境の中で一所懸命経営するわけですが、皆、スーパーマンや聖人ではないわけです。1つは、権力者の絶対権力はいつか腐敗するという、その腐敗するリスクというか危険性に対して、だらしなくなってしまうという危険性をどう律するかという問題が常にあります。基本的に、企業は組織構造です。ある種の権力的組織構造ですから、長期的には必ずこの問題があるわけです。これが1つです。もう1つは、人間の能力は有限という点です。特に今は、イノベーションという要因でも、グローバル競争という要因でも、環境が極めて大きく振れるわけです。いろいろな「えっ」と思うようなことが突然現れてくるわけです。ですから、そういう状況下で、過去の経験とか社内で持っている見識であるとか、その中で全部対応できるかというと、それはやはり限界があると思います。
そうすると、私から見ると2つの大きなダウンサイドでありアップサイドでもあるこれらの問題に対して、世の中にあるいろいろな知恵なりあるいは経験なり規律なりを、どこまで経営に持ち込めるかということは、かなり本質的な問題です。それを、いわゆる新卒一括採用で入って、ずっと終身雇用で一緒に働いてきた人たちの組織やボードや経営者だけで対応できるかというと、多分、もうそういう時代ではないのです。なので、そこにガバナンスが必要になるわけです。
今いる経営者がどうかという問題も、将来的にどのような経営者を選ぶかという問題も、実は同じことです。さきほどの腐敗に対する規律とは、最終的には腐敗したら交代してもらうということなのですが、そうすると今度は、交代させるにしても次にいい人がいなかったら簡単に交代してもらうというわけにいきません。だからこういった議論を突き詰めていくと、経営者、経営陣というものを、どれだけ最良の状態に保てるかということになり、私はそれが経営上の最重要課題だと思っています。そうすると結局、どのようにしてその経営者、経営陣は選ばれているのかという基本構造の話に戻るわけです。その観点で企業統治の構造、投資機構の議論にかなり関心を深めていくと、つまるところ、会社法が定めている統治構造というのは代議制資本民主制なのです。要は、年に1回株主総会という形で、総選挙を行う。
松本:
議院内閣制みたいな感じですね。
冨山:
まさにそうです。その総選挙で取締役のメンバーを選ぶわけです。いわば国会議員、代議士を選ぶわけです。その代議士の多数で、内閣総理大臣を選ぶ。これが経営者です。こういった仕組みになっているわけです。では誰がそこにかかわっているのか。まず先に資本民主主義があります。資本民主主義の議院内閣制です。その資本民主主義を担っているのが株主ですよね。だから株主がきちんとしてくれないと、「えっ」という人が国会議員になってしまって、「えっ」という人が総理大臣になったり大統領になったりしてしまいます。ですから、この株主の人たちの民度、あるいはやる気の問題は、極めて大事です。これがしっかりしていて、しっかりとした国会議員を選んでくれて、この国会議員がしっかり真面目に仕事をしてくれて、初めてまともな総理大臣が選ばれるし、もし総理大臣に問題があったら、不信任で交代させるし、場合によっては総選挙に訴えて総選挙の結果として代議士が入れ替わるのです。少なくとも、そういったダイナミズムが働くような圧力がかかっていないと、しっかりした経営陣を維持できなくなるはずなので、私は、こういった時代において、ガバナンスがきちんと機能するかどうかということは、企業の成長、競争に決定的な意味合いをもつと思っています。
松本:
いくつか論点があったと思うのですが、1つずつお伺いしていきたいと思います。経営者と経営陣、両方の言葉を使われていましたが、企業の出力に対する経営者の重みというのは、経営陣というか経営体から見て、どの位個人のウエートが大きいのでしょうか。
冨山:
これは業態とかビジネスにもよると思いますが、少なくともイノベーション・ストレスがかなり強い、あるいは競争のストレスがきついところにおいては、今日的には経営者の役割は、企業体そのものの組織能力の限界的なところでの戦いになるので、7~8割位になると思っています。
松本:
それはおっしゃっていた、腐敗の問題と、環境が大きく振れる中でいわゆる会社員だけで対応できるのかという問題でいうと、後者の問題が増えてきていますか。
冨山:
はい、後者のほうが厳しくなっています。かじ取りの幅が、20年前だったら、組織体自身(現場サイド)が持っている変容・変異の幅で、大体、対応できたのです。日本型の現場主義型経営で、生産プロセスが自律的にいろいろな状況に対応できた。
松本:
会社に元々ある幅で対応可能だった。
冨山:
はい、対応可能でした。また、事業ポートフォリオもそこまでドラスティックに入替えしなくても大丈夫だったのです。ところが今は、結構大きな事業でも消えてしまったりします。例えば、電機メーカーでは、テレビという事業はもう収益事業としては消えてしまっているわけです。圧倒的に大きかった事業が、数年でポーンと消える。それから携帯電話も、iPhoneが出てきてしまって、日本型の携帯電話モデルがある日突然消えるわけです。こういうことが瞬時に起きてしまい、今手持ちの現場力だけでは対応できない問題なので、司令官が相当大胆な舵を切る必要がある。あるいは、今の組織能力で対応できないのであればその事業をあきらめるのか、逆に新しい組織能力をM&Aなりかなり大胆な採用によって取り入れるのかということを決定していかなくてはならなくて、こういったことはやはりトップリーダーが推進する必要があります。ボトムアップではそういう話は出てきませんから。そうすると結局、問題は、その経営者がしっかり仕事をしているかどうかということになります。
松本:
チームの多様性という幅の中で対応できることは、その中でするのですが、そこから外に出てしまっているものとか、チームごと動いていかなければならない場合には、チームの性質として、チーム全体で決めるのはなかなか難しくて、それは司令官がしなければいけないということですね。
冨山:
チームはどうしても現状維持的になりますから。あるいは、「自分たちはできる」と言いますから。
松本:
そういう場合に、外部からの知恵や意見が、かなり有効だということですね。
冨山:
そう思います。そういう視点で見られる人物がいることが前提ですが。
松本:
会社内に、それを受ける体制がなければいけないということですね。
冨山:
そういうものも、結局トップ次第ですよね。一番受けなければならないのはトップです。トップが受けられないものを、他の人が受けるといっても意味がない。その働きかけを、例えば社外取締役がするのか、あるいは株主の中でそういう働きかけをしてくれる人がいるのかということになります。もちろん、本来、経営陣は、競争相手からそれを受け取らなければいけないのですが、どうしても、そのときには、現状でできるというバイアスがかかるので。
松本:
何とかなるだろうと。
冨山:
そうです。要は、今までやってきた種目が野球からサッカー位にまで変わってしまっていて、そこは認識するわけですが、それはやはり人間の性(さが)として、大体の反応は、自分たちは運動神経がいい、体力もあるから対応できるといったものになりがちです。
松本:
野球でここまでやってきたからサッカーでも勝てると。
冨山:
そうです。ですから、野球をやってきた人たちにこれからサッカーを練習して、となるわけです。日本のエレクトロニクスが負けてきているのは大体これですから。今も、一所懸命、普通のソフトエンジニアにAIを勉強しろ、Python(パイソン・プログラミング言語)を勉強しろとやっているわけです。それである程度はうまくなるのですが、AIがガッと入ってきたときに、低いレイヤーではなくて、一番上のレイヤーをつくるものが本当のビジネスの勘所なのです。結局、サッカーをしようとしているのに、ずっと野球をしていた選手にやらせる。皆運動神経がいいからある程度は上手くなりますが、実際の競争というのは、残念ながらJリーグではなくて、グローバル競争だからそれはチャンピオンズリーグなわけです。そうすると、ピッチに立ってみたら、向こう側にメッシとかロナウドがいるわけです。そうするとボコボコにされますよね。そうやってGAFAとかにボコボコにされてきたのが、この30年間です。

啐啄(そったく)同時―外からの刺激との釣り合い
松本:
最近の話題だと、ラグビーで日本がベスト8までいきました。あれはコーチが外国の方でしたね。
冨山:
ニュージーランドの方でした。
松本:
選手もかなり多彩でグローバルです。若干話を引き込みすぎかもしれませんが、日本の企業の今後の在り方として、何かヒントがあるのではないですか。
冨山:
あると思います。20年位前にニュージーランド相手に百何十対いくつかで負けましたよね。ラグビーで100点取られるのは大変ですよ。
松本:
あれは、チームのメンバーがグローバル化したという部分と、コーチがグローバルな人だったというのと、どちらの影響が大きいのでしょうか。あるいはラグビーはどちらか分かりませんが、少なくとも企業だとどうでしょう。
冨山:
ラグビーでは、その上のレベルにいる人たち、企業でいうところの経営者が、かなり時間がかかっても仕方ないから、あのように選手も多様化する、現場監督ももう日本人にこだわらないという選択をしたわけですよね。ただ、ラグビーはチームスポーツですから、あれをワンチームとして機能させようとすると、一朝一夕では無理です。おそらく、高校や大学からどんどん外国人を受け入れてきて、彼らが日本に定着してきたというプロセスがあったでしょう。確かコーチも日本のどこかのチームでプレーした人でした。会社であれば、会社の特性をよく理解した上で、多様性を取り込んで、多様性がちゃんとワンチームで機能するようにするという、ある種のトランスフォーメーションをきちんとしてきた結果だと思います。そういうかなり時間を必要とするトランスフォーメーションを誰がするのかといったら、それはもう経営トップしかあり得ません。あるいはボードがそれをサポートするしかないわけです。それが、従来の日本型のような、どちらかというと新卒一括採用で、ずっと同じ組織の中で、野球しかしたことのない人だけでやろうとしても、それは厳しいですよね。
松本:
純血主義になってしまうと厳しいですね。私は、好きなというか、気になる言葉に、啐啄(そったく)という言葉があります。卵の中から雛が出ようとしてつつくのが啐、母親が外側から叩くのが啄で、啐啄同時という禅の言葉です。要はタイミングが合うということです。中からも出ようとしていて、そのときに外から助けてあげると、すっと出られると。中から出ようとしていないのに叩いてもいけないし、中からだけ頑張っていても出られないという、そういう同時に起きることが大切だという言葉ですが、企業の変化や変革をするときに、こういう内側から変わろうとするもの、今のラグビーの話でも中から準備されてきたものもあると思うのですが、それと、外からのものの釣り合いは、どのような場合に、一番うまく会社が変われるのでしょうか。
冨山:
これは私の実感でいってもグッドポイントで、会社自身が本気で変わらなければいけないという思い、あるいは、経営者なり経営陣なりが、本気で変わらなければいけないという思いがあって、そこにまさに外からのアクションがあって、それらが啐啄同時といいますか、ビジョンを共有しながら、それをエンカレッジして刺激するというのが同時に働くと、一番うまく変わることができるのはそのとおりだと思います。
松本:
うまくタイミングが合わないと駄目ということですよね。
冨山:
そうです。私が社外取締役を引き受けるときに条件にしていることがあります。本気でトランスフォーメーションをする気があるのかということです。例えば会社の命運を左右するような議案がおかしいと思ったら、平気で止めます。場合によっては、外部にもこれはおかしいと言います。社長に焼きが回っていると思ったら、最悪、解任動議を出します。次の後任の選任に関しても、本気で関わります。これら全部を本当にしますがいいですか?というのを条件にします。
松本:
その相手は経営者ですか、それとも株主ですか。
冨山:
現状は経営者ですね。ただ、株主で僕のことを知っている人は、どういう人か分かっているはずなので、嫌だと思ったら反対するでしょう。こうしてどんどんハードルを上げていくと、意外と社外取締役は頼まれないです。
松本:
議院内閣制のような仕組みで考えると、一方に会社があり、現代においてその会社を動かしている、重要なカギを握っているのは経営者で、もう一方に株主という有権者がいます。有権者が会社に何か変わってほしいと思ったときに、変わってもらうためのメディアというか媒体として今考えられるのは社外取締役が一番大きいですか。
冨山:
それは今のところは社外取締役ですね。ただもちろんのことですが、総選挙が1年に1回あるわけなので、そのときに総理大臣が語りかけなければいけないのは、有権者に対してなのです。だから、健全なガバナンスとして、毎月あるいは2ヶ月に1回ぐらいは、取締役会という「国会」で社外取締役と対峙をするわけです。ですが、それに加えて、直接国民との対話が必要なわけです。

株主総会の在り方を考える
松本:
有権者に対するエンゲージメントですね。
冨山:
両方機能しないといけません。
松本:
私は今、Mastercardの取締役をしているので、アメリカのそれを目の前でよく見ているのですが、アメリカでは、エンゲージメントというのは総会の前に起きることではなくて、1年中起きているのです。1年中、経営者・企業と株主の間で会話がなされていて、サクセッションプランとかも含めて、いろいろな話がされています。そこでいろいろな会話がされた上で、出来上がりとして議案が出てきて、議案が出てくるときにはもう既にエンゲージメントはほぼ終わっていて、結果として議案も整理されています。ですから、実は、アメリカの株主総会では波乱は案外ない。
冨山:
アメリカの株主総会はすごく予定調和的ですね。
松本:
もうエンゲージメントは終わっているのですね。日本は逆に、期中のエンゲージメントがすごく足りなくて、総会一点主義。総会で急に持ち込むような感じがあるように思います。それはやはり直していかないといけない。
冨山:
あまり生産的でもないです。そこに全部を入れ込むのは無理です。
松本:
しかも日本の場合、総会が6月に集中しています。
冨山:
たった3時間程度では無理ですよ。株主総会というのは、ある種大衆的な投票局面ですから、実はそこだけで内閣の評価はできないわけです。ということは、日常的にどれだけ建設的対話がなされたか、国会での議論、実際の有権者が関わっているところで総理が何を語りかけたか。それに対してどういう反応があったかという世論調査が日々出る。そういう状況の蓄積があっての総選挙です。それが、ある日突然何もないところで急に、はい選挙行います、となったら有権者も機能できないです。
松本:
伊藤レポートなどいろいろ作られた審議会があったときに、私もメンバーだったのですが、総会の在り方を考える部会のようなものもありました。私は、1つ随分強く提案したものがあって、それは、取締役選任議案は一定の条件を満たした株主しか提出できないというようにしてしまうというものです。
冨山:
それは正しいですね。私もずっと言っています。
松本:
そうすると、経営は、その人たちと話すようになるはずなのです。
冨山:
日本の株主提案は、提案するのが目的になってしまいがちです。そもそも株主総会における最も重要な議案は取締役選任議案です。アメリカの総会は、すごく決められることが限られていて、ほとんどは取締役会に移譲されてしまっています。本当は、総会というのは最後の最後のイベントで、その前に決着をつけておかないとおかしいのです。そう考えると、やはり、株主、それもある程度のリテラシー・見識を持って日常的に経営者と対峙できるようなクオリティーを持っている株主、それからその付託に値するだけの社外取締役、この2つの条件が機能しないと、ガバナンスは機能しないです。
松本:
そうですよね。
冨山:
ですが、残念ながら、2つとも、日本は割と欠如していたわけです。一応、社外取締役は、形式上入るようになりましたが、ここは今、その付託を受けるだけの立派な代議士か?という問題がいわれているわけで、クオリティーは当然上げなければいけません。ただ、このクオリティーを上げるためには、本人たちも頑張らなければいけないのですが、これを選んでいる側が、しっかりとそういう規律をこの人たちに働かせておかないと、このクオリティーは上がらないです。というのも、結局、株主は直接には社長を選んでいるわけではなく、与党議員を選ぶわけでしょう。ですから、「えっ」と思うような人が与党議員になってしまうと、「えっ」という人を社長にしてしまいます。
- 冨山氏×松本対談 PART1
- 冨山氏×松本対談 PART2