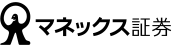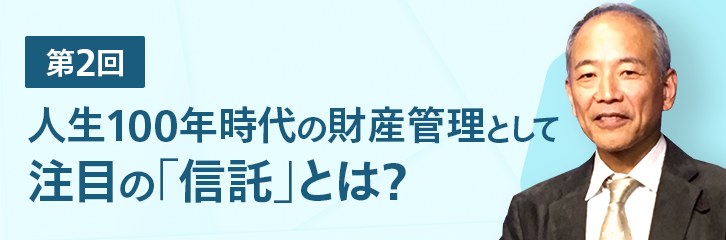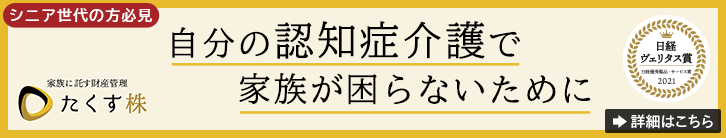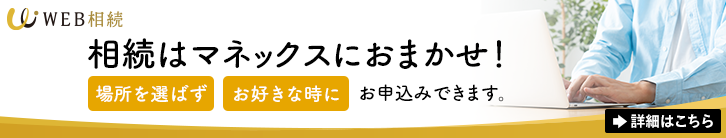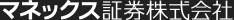資産承継コンサルタントの永井勝巳氏へのインタビューの第二回目です。第一回目は、円満な相続のために、気をつけるべきこと等をお伺いしました。第二回目では、「遺言」や「信託」といった相続対策にも触れて、具体的に何をやったらいいのかを教えていただきました。

資産承継コンサルタント
永井 勝巳 氏
1975年 三井信託銀行入社 中央信託・住友信託との合併を経て
2016年 三井住友信託銀行 プライベートバンキング部 上級主席財務コンサルタントを最後に退職。
同年よりファイナンシャルプランナーとして相続を中心にコンサルタント活動開始。
成蹊大学 経済学部 非常勤講師 「信託の理論と実際」
著書 「財コン!円満相続への案内人!」(幻冬舎)他
人生100年時代の財産管理として注目の「信託」とは?
-オンライン証券のお客様から個別相談を受けてみて、どうですか。
永井氏:
マネックス証券で月に一度、無料のオンライン相談を1年以上続けていますが、ご相談の内容は信託銀行の頃のお客様とほとんど変わりません。ただ、ご自身で資産運用をされてきた方が多いので、まだまだ資産を固めて資産配分を検討することは決めかねているようですし、遺言を作ったり、信託を組んだりといった相続対策には、消極的なケースも多いように感じます。年齢が比較的若い方が多いので、ご自身の判断力が衰えたり、その先には相続がある、といったことがまだ想像しづらいのかもしれません。
でも、対策というのは、「元気なうち」にするのが良いのです。遺言を作っておくことや信託も選択肢として考えていただきたい。最近よく言われている家族信託についても知っておいていただきたいですね。
私がこう言うのも、残念ながら、手遅れになってしまう人を見てきたからなんです。昔、担当したお客様で、前任のコンサルタントが「遺言を書きましょう。」と提案してから、私の担当期間と合わせて5、6年が経ってもまだ悩みに悩んで、結局書かずに亡くなってしまった方がいらっしゃいました。
-円満な相続の決め手は遺言ということでしたが、「信託」という選択肢も話に挙がりました。
永井氏:
相続対策の決め手と言われる「遺言」ですが、その効力が発揮されるのは、相続発生後になりますね。ただ、人生100年時代とも言われる現代においては、相続の前に、ご自身が認知症になったり介護を受ける可能性があることに十分に備えておかなければなりません。
自分だけでなく、身の回りのサポートや介護をする家族が困らないようにする視点が大事です。その対策の一つとして有効なのが「信託」です。
実は、要介護(要支援含む)認定を受けるのは70~74歳の年代では5.8%程度ですが、75~79歳となると、12.7%と倍増します。75歳までには考え始めたいですね。
-「信託」について、よく分かっていないので、教えてください。
永井氏:
信託そのものの説明の前に、まずは、シニア世代にどんな困りごとがあるかを説明しますね。信託はこの困りごとに備えるものなのです。
75歳の母と45歳の子という家庭を例に説明します。
母が認知症になってしまった場合、金融機関の口座取引が制限されることはご存じですか。本人だけではなく、家族であってもお金が引き出せなくなります。いわゆる口座凍結です。
母の銀行口座には、父の相続時に受け継いだまとまった資金があることが多いです。金額としては、介護に充てるのに十分であったとしても引き出せない、ということが起こるわけです。
株式を持ってる場合にも、本人でないと売却ができないので、特に相場が下落している時などは、家族は何もできずに困ってしまいます。
また、お金の出し入れが制限されるだけでなく、母が介護施設に入ることになり、自宅を売って入居一時金を捻出しようとしても、所有者である母は契約ができないので自宅の売却もできません。そこまで想定していない方も多く意外な落とし穴かもしれません。
結果、40代の子に、必要な資金を立て替える必要が出るのですが、この年代は子供の教育費や住宅資金等にお金がかかる時期でもあり、兄弟姉妹間で、誰が出すのか揉める恐れもありますね。

ここで、話を信託の説明に戻します。信託は、こういったシニア世代の困りごとに備えて、母の判断能力が不十分になった時でも、家族が母に代わってお金を引き出して介護費用の支払いに充てたり、自宅を売却したりすることを可能にする制度なのです。
法律的に言うと、信託とは、「財産を所有する人」が「信頼できる人」に財産を渡して、自分の希望する目的のために財産の管理・処分などの法律行為をしてもらう制度、となります。
「財産を所有する人」を委託者、財産を渡される「信頼できる人」を受託者といいます。
-「信託」の利用について、お客様が詳しく知りたい、相談したいという場合に、どうすれば良いでしょうか。
永井氏:
近年、信託の仕組みを使って認知症対策や相続対策をすることが、少しずつ浸透し始めたところです。
マネックス証券では、株式の認知症・相続対策として「たくす株」という信託を使ったサービスを代理店として取扱っています。証券会社と信託会社を持つマネックスグループならではのサービスですね。
また、預金や不動産を対象として、最近注目されている「家族信託」を手軽に始められる「つむぎ」というサービスをマネックスSP信託が提供しています。
定期的に無料相談を開催していますので、自分のニーズに合うものか是非ご相談にいらっしゃってください。
Zoom等を使ったオンライン面談ですので、自宅にいながら相談できて気軽ですよね。
円満な相続のために
-最後に、ずばり何をやっておけば円満な相続になるのか教えてください。
永井氏:
シニア世代の財産管理や相続を考えるには、まず家族の関係、財産の内容や状況、そして自分の希望の3点をミックスして考えることが必要です。自分の考えだけが先行してしまうと子供たちから見れば不公平な配分になってしまうこともあります。
自分の家族ではどのような対策が必要なのかを知った上で専門家に相談することが、円満な相続への近道でしょう。
マネックスグループでは、先に紹介した「たくす株」「つむぎ(家族信託)」に加え、相続手続きの代行サービス「WEB相続」等、シニア世代の困りごとをサポートする体制を整えています。
まずは知ることから始まるので、気軽に相談してみるのが良いのではないでしょうか。
-インタビューをありがとうございました。
資産継承対策に「たくす株」
「たくす株」は「信託」という仕組みを活用し、お客様のご資産のうち国内上場株式等について、将来の不測の事態に備えて財産管理方法や資産継承先をあらかじめ決めておける有価証券管理信託です。老後の投資生活を安心して楽しむために、マネックスで資産承継対策を始めてみませんか。
※たくす株はマネックスSP信託のサービスです。マネックス証券はマネックスSP信託の代理店としてご案内しています。
相続の手続代行をお考えならマネックスへ
相続手続きをしなければならないけど、手続きはやることがたくさんで煩雑だし、忙しくて時間がない......手続を代行してもらえるならお願いしたいけど、どこに頼んだらよいか分からない......
マネックスのWEB相続は、そんなお客様に代わりに金融資産や自宅不動産の相続手続きを行うサービスです。お申込みはインターネットから24時間可能で安心の報酬体系。まずはウェブサイトより詳細をご覧ください。
「WEB相続」は、マネックスSP信託のサービスです。マネックス証券はマネックスSP信託の代理店としてご案内しています。
信託・相続支援センターへご相談ください

将来に備えた財産管理、相続のお悩みは専属の担当者がサポートします。
- FP資格を保有する専門スタッフが対応
- お客様毎に1人の担当者が継続してサポートいたします。
- お忙しい方でもご相談予約が可能
- オンラインで担当者と顔を合わせて相談ができます。
 マネックス証券 信託・相続支援センター
マネックス証券 信託・相続支援センター
営業時間 平日 8:00~17:00
固定電話から(通話料無料)
携帯・スマートフォンから(通話料有料)