遺言は認知症にそなえた相続対策として有効です。
認知症と判断されたときの財産管理・運用・処分はできなくなりますが、「どの財産を誰に渡すか」については希望通りに実現しやすくなります。
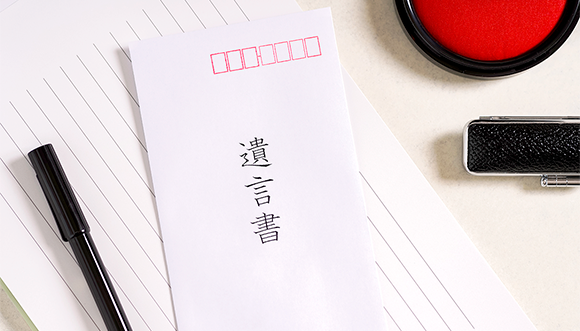
| 家族信託 | 遺言 | 生前贈与 | |
|---|---|---|---|
| 効力を巡る相続争い対策 | △(※) | △(※) | △(※) |
| 財産承継対策 (財産を渡す相手を選べるか) |
◎ | ◎ | ◎ |
| 相続税対策 | × | × | 〇 |
| 認知症になったときの財産管理対策 | ◎ | × | × |
| 費用 | 30万- 100万円 |
数万- 50万円 |
1万- 25万円 |
「◎」:最適
「〇」:適している
「△」:注意が必要
「×」:適していない
※効力を巡る相続争い対策について、公正証書で文書を作成した場合効果あり
遺言とは、生前に「自分が亡くなった後、どの財産を誰にどれだけ相続させるのか」という内容を書き残した文書のことです。遺言があると、相続人は原則遺言の内容通りに遺産分割を行うことになります。
遺言には、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類ありますが、認知症にそなえるためには、「契約した時点では意思能力があった」ことを証明できるよう、公正証書遺言で作成するのがよいでしょう。
【公正証書遺言の特徴】
遺言には大きく次のようなメリットが挙げられます。
遺言の最大のメリットが、相続財産の分け方を自分で決められる点です。
自分が渡したい人に財産を渡すことができ、相続人が財産の分け方でもめることも防げます。法定相続分とは異なる割合にすることもでき、特定の財産の承継先を指定することもできます。また、財産を渡す相手に相続人以外の人または法人を指定することもできます。
家族信託は対象財産が「信託した財産」のみであるのに対し、遺言は「亡くなった時点の財産」なので、より広い範囲の財産をカバーできます。
遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う「遺言執行者」を指定することができます。
具体的には、遺言執行者は相続財産目録を作成したり、各金融機関での口座解約手続きや不動産名義変更手続きなどを行う権限を持ちます。
司法書士等の専門家を遺言執行者とすると、ノウハウがあり手続きがスムーズとなるうえ、第三者が間に入ることで相続人同士でもめることを回避できるといったメリットもあります。
家族信託や生前贈与と異なり、遺言は相手の同意が必要ありません。一方的に作成でき、いつでも書き換えや撤回が可能です。公正証書遺言で作成していた場合、書き換えや撤回時も公証役場で手続きします。
一般的に遺言のデメリットとしては、紛失・偽造・変造・形式不備による無効などのリスクが挙げられますが、公正証書遺言はこれらのリスクは極めて低いので、安心して作成することができます。
遺言自体は相続税の節税対策にはなりません。
ただし、相続税には様々な特例や控除があるので、それらの制度を活用できるように上手く財産分配を考えれば、税負担の軽減は期待できます。
公正証書遺言の作成は、証人2人以上の立ち合いが必要(民法第969条)なので、証人を探す手間がかかります。次にあてはまる人は証人にはなれないので、証人にふさわしい人を探すのは簡単ではないでしょう。
【証人になれない人】
適切な証人を自分で探せない場合は、公証人役場に紹介してもらったり、弁護士や司法書士などに依頼したりする方法があります。
公正証書遺言作成にかかる費用は総額で数万~50万円ほどで、内訳は大きく分けると次の通りです。
| 項目 | 目安 | |
|---|---|---|
| 実費 | 公正証書作成費用※ | 1万~25万円 |
| 証人への報酬 | 5千~2万円 | |
| 専門家への公正証書作成代行の報酬 | 10万~25万円 | |
※謄本手数料などを含む
遺言を作成してから相続を迎えるまでには時間が経過します。その間に財産の内容や財産を渡すために指定した人にも変化が生じます。相続時に遺言通りに財産が分けられるようにするためには、そうした変化も想定した内容の遺言に整える必要があります。
しっかりとした遺言を作成するには、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。