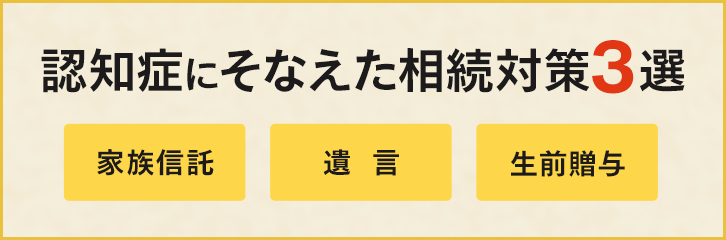
いまや国民病ともいわれる認知症。ご自身や、親が認知症になった時のことを考えて、今後のことに不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。本コンテンツでは認知症にまつわる相続についての影響やその対策などを詳しく解説します。
認知症が進む前に対策をしておくことの重要性を理解いただくことで、自分たちに合った相続対策を選択できるかもしれません。
【本コンテンツで分かること】
大前提として、認知症と判断されると相続対策はできなくなります。たとえば、認知症になってから遺言を作成したとしても、無効になってしまいます。
(民法第3条の2:法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする)
この「法律行為」とは、契約や合意に基づいて成立する行為や、遺言など一方的な意思表示で成立する単独行為のことも指すため、相続に関する様々な対策も該当します。
よって、認知症と判断されると以下の行為は行うことができず、仮に行ったとしても認知症と判明すれば無効とされます。

【認知症と判断された後では行えない相続対策】
また、最も影響する事態として、預金口座の引落ができなくなります。金融機関は口座名義人が認知症であると判断すると、口座の不正使用などのトラブル防止のため口座を凍結します。
その結果、何も対策ができないまま相続を迎えることになるため、意思能力がまだあるうちに必要な対策を講じることが重要です。

相続対策を何もしないまま親が認知症と診断されたり、認知症が進行しているにも関わらず、無理に相続対策を行なったりすると、様々な相続トラブルが発生する可能性が高まります。
【親が認知症と判断された結果起こる相続トラブル】
このようなトラブルを防ぐためには、まだ意思能力があるうちに対策しておく必要があり、かつ「意思能力があった」ことを証明できるようにしておくことも重要です。
これは、後になって他の相続人が「遺言を書いたときはすでに認知症だったから遺言は無効である」などと主張してくる可能性もあるためです。
認知症にそなえトラブルを防ぐための対策として、3つの対策を紹介します。いずれかひとつでも効果はありますが、複数を組み合わせて対策すればより安心です。各対策にはそれぞれカバーできる範囲が異なるので、複数行うことで相互にデメリットを補えます。
認知症により起こる相続トラブルをふまえて、各相続対策の特徴を下表にまとめました。
| 家族信託 | 遺言 | 生前贈与 | |
|---|---|---|---|
| 効力を巡る相続争い対策 | △(※) | △(※) | △(※) |
| 財産承継対策 (財産を渡す相手を選べるか) |
◎ | ◎ | ◎ |
| 相続税対策 | × | × | 〇 |
| 認知症になったときの財産管理対策 | ◎ | × | × |
| 費用 | 30万- 100万円 |
数万- 50万円 |
1万- 25万円 |
「◎」:最適
「〇」:適している
「△」:注意が必要
「×」:適していない
※効力を巡る相続争い対策について、公正証書で文書を作成した場合効果あり
認知症にそなえた相続対策として総合的に効果が高いのは家族信託なので、まずとりかかるとしたら家族信託がおすすめです。
部分的な対策でよければ、その項目に「◎」がついている相続対策を優先的に進めていくとよいでしょう。
認知症の症状がどの程度で意思能力がないと見なされるのかの基準ですが、認知症とひとくくりにされても、まだ軽度であったり、日によっては調子がいい時もあると思います。
たとえば、銀行は下記のような行動ができない場合に認知症と判断することがあります。
対応する各機関や法人によっても判断基準は多少異なりますが、担当者が本人と直接やり取りをして、総合的に意思能力の有無を確認します。金融機関では意思能力に問題ありと判断した場合、口座を凍結することがあります。